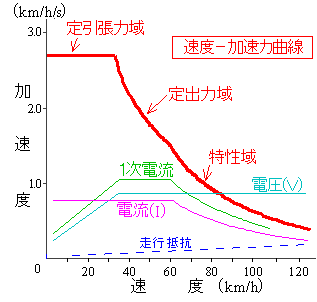4丏 幵椉偺椡峴惂屼偲偼丠 曄揹強偲偺娭學偼丠
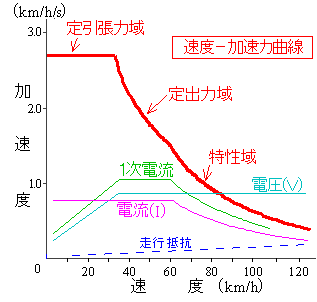
1. 揹幵偺壛懍摿惈
丂 俰俼惣擔杮偺搶惣慄偵搳擖偝傟偰偄傞庡椡捠嬑揹幵偺婎杮僗儁僢僋偼丄
- 僗僥儞儗僗20m挿幵懱偺7椉乮3M[揹摦幵]丒4俿[晅悘幵]乯曇惉丅
- 1曇惉偺塣揮惍旛廳検202倲丄壸廳16倲/幵乮惈擻専摙梡丗180亾憡摉丠乯偲偟偰曇惉幙検偼314倲丅
- VVVF僀儞僶乕僞惂屼桿摫揹摦婡嬱摦丅揹摦婡偺掕奿弌椡155kW丅
- 婲摦壛懍搙2.7km/h/s丄嵟崅懍搙120km/h丅
偲側偭偰偄傑偡丅
丂 幵椉偺惈擻傪敾抐偡傞曽朄偼怓乆偁傝傑偡偑丄楍幵偺懍搙偲偦偺懍搙偱偺壛懍椡乮堷挘椡乯傪帵偡懍搙亅壛懍椡摿惈偼
嵟傕廳梫側傕偺偺1偮偱丄塃恾偼偦偺搶惣慄偺捠嬑揹幵偺傕偺偺堦晹偱偡丅
丂 愒偄慄偑壛懍椡傪帵偡慄偱丄懍搙偵墳偠偰堦斒偵師偺傛偆側屇傃曽傪偟傑偡丅
嘆掕堷挘椡堟
丂 堦掕偺壛懍椡偱壛懍偡傞傛偆偵惂屼偡傞斖埻丅
丂 婲摦帪偺壛懍搙偱嵟崅懍搙傑偱壛懍偡傞偲丄俹(弌椡)亖俥(壛懍椡)亊V(懍搙)偐傜戝偒側弌椡偑昁梫偵側傝丄曄揹強偺梕検摍偺柺偱柍懯偵側傞偺偱丄
偁傞懍搙乮塃恾偱偼栺35km/h乯埲忋偵側傞偲丄俹亖俥V亖堦掕丂偲側傞嘇偺掕弌椡堟偵堏峴偡傞傛偆幵椉偺惂屼憰抲偱惂屼偟傑偡丅
嘇掕弌椡堟
丂 壛懍椡亊懍搙乮亖弌椡乯偑堦掕偵側傞傛偆偵惂屼偡傞斖埻丅
丂 幵椉偲偟偰嵟戝偺弌椡傪敪婗偡傞懍搙堟偱偡丅
嘊摿惈堟
丂 壛懍椡偑懍搙偺傎傏2忔偵斀斾椺偟偰尭彮偟偰備偔斖埻丅懍搙偼忋偑偭偰偄偒傑偡偑丄弌椡偼嘇傛傝抜乆尭偭偰偄偒傑偡丅
2. 壛懍搙偲堷挘椡偺娭學
丂 幙検1倲偺暔懱傪1km/h/s偺壛懍搙偱墴偡偨傔偵偼31kgf偺椡偑昁梫乮倖 = m丒兛偐傜偼28.34偱傛偄偑丄 夞揮晹壛懍椡傪峫椂偟偰31偲偡傞)側偺偱丄7椉曇惉314倲傪壛懍偡傞偨傔偵偼嘆偺斖埻偱偼
2.7km/h/s亊31亊314倲亖26,300kgf
偺椡偑昁梫丅儌乕僞乕1屄偁偨傝丄栺2,200kgf偵側傝傑偡丅
丂 懍搙亅堷挘椡摿惈偱偼廲幉偵偙偺堷挘椡乮偨偲偊偽丄儌乕僞乕1屄摉偨傝乯傪昞帵偡傞椺偑懡偄偺偱丄忋婰偺幃傪巊偭偰壛懍搙偵曄姺偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅
傑偨丄偨偲偊偽15侎偺搊傝岡攝傪忋傞偲偒丄15/31亖0.48乮km/h/s乯偲側傝丄偙偺暘偩偗幵椉偺壛懍搙偑尭傞偲偄偆傛偆側巊偄曽偑偱偒傑偡丅
3. 掕弌椡堟偱偺弌椡
丂 嘇偺斖埻偱偼丄幵椉偲偟偰師偺傛偆側嵟戝弌椡傪弌偟傑偡丅
35km/h亊26,300kgf亖9.7(m/s)亊26300亊9.8/1000亖2,500kW乛7椉曇惉
丂 幵椉巇條忋偼丄揹摦婡偺弌椡亖155kW偱偡偐傜丄曇惉偱偼
155kW亊3M幵亊4屄/M幵亖1860kW乛7椉曇惉
偲側傝丄2,500kW傛傝彫偝偄抣偱偡偑丄2,500kW偼嵟戝抣丄1860kW偼1帪娫掕奿偱丄偦偺慄嬫慡懱傪塣揮偟偨応崌偺堦庬偺戙昞抣偱偡丅幚嵺偵偼憱峴僔儈儏儗乕僔儑儞偱
儌乕僞乕偺掕奿摍偺彅悢抣傪寛傔傞傛偆偱偡丅
4. 揹埑偲揹棳
丂 揹棳丄揹埑偺嵶慄(僗働乕儖側偟)偑偁傝傑偡偑丄偙傟偼揹摦婡偵偐偐傞傕偺偱懍搙偵墳偠偰惂屼偝傟傑偡丅岎棳揹摦婡偱偼廃攇悢傕惂屼偝傟傑偡丅偙傟傜偼偁偔傑偱
揹摦婡1戜偵偐偐傞傕偺偱丄幵椉偲偟偰廤揹偟偰偄傞僷儞僞僌儔僼揰偱偼揹埑偼曄摦傪柍帇偡傟偽偒揹揹埑偱堦掕乮捈棳側傜1500V乯偱丄廤揹揹棳偑曄壔偡傞偙偲偵側傝傑偡丅
5. 1師揹棳
丂 僷儞僞僌儔僼揰偱偺廤揹揹棳偱偡丅晧壸偵傛傝懡彮曄摦偟傑偡偑丄捈棳偒揹偱偼壦慄偵偼1500V偺堦掕揹埑偑偐偐偭偰偍傝丄揹棳偼偙偺慄偺傛偆偵曄壔偟傑偡丅
揹埑偼堦掕偱偡偐傜丄揹棳偑嵟戝偱偁傞35乣60km/h偺斖埻偱嵟戝揹椡傪徚旓偟偰偄傞偺偑傢偐傝傑偡丅
6. 曄揹強偺棫応偐傜幵椉傪尒傞
丂 揹幵撪偱偼儌乕僞乕偺揹埑偲揹棳傪嵶偐偔惂屼偟偰偄傑偡偑丄幵椉偵揹椡傪嫙媼偡傞曄揹強偐傜傒傞偲扨弮偵丄
| 婲摦乣35km/h | 丂 | 丂0kW仺2,500kW丂偵傎傏堦掕偵憹壛偡傞丅 |
| 35乣60km/h | 丂 | 丂2,500kW丂偱堦掕丅 |
| 60km/h埲忋 | 丂 | 丂2,500kW丂偐傜摿惈偵墳偠偰尭偭偰偄偔丅 |
偲懍搙偵墳偠偰曄摦偡傞晧壸偑偁傞偲尒偊傞偩偗偱偡丅
丂 曄揹強偱偼丄P(弌椡)亖F(椡)丒V(懍搙)偱側偔丄P(弌椡)=E(揹埑)丒俬(揹棳)偱尒傑偡偐傜丄揹埑1500V偱揹婥傪憲傞応崌偼
嵟戝揹棳偼丄曇惉崌寁偱2500kW乛1500V=1670A丂偲側傝傑偡丅
丂 幚嵺偵偼丄幵椉偺嬻挷婡摍偺曗婡椶傗奺婡婍摍偺懝幐暘傪尒崬傓偺偱傕偭偲戝偒側揹棳偑棳傟傑偡丅
丂 岎棳偒揹偺応崌偼丄椡棪傪峫椂偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅僒僀儕僗僞埵憡惂屼幵偱偼揹婥幵偺晧壸椡棪偼椡峴帪0.7乣0.8丄夞惗帪亅0.4乣亅0.5掱搙偱偟偨偑丄 嵟嬤偺PWM惂屼幵偼椡峴帪1丄夞惗帪亅1傪栚昗偵惂屼偝傟偰偄傞偦偆偱丄VVV俥僀儞僶乕僞惂屼幵偼偙偺柺偱傕桪傟偰偄傑偡丅
7. 揹埑崀壓
丂 揹幵偑憱傞偲丄曄揹強仺楍幵娫偺揹棳亊壦慄掞峈丂偵傛傝揹埑崀壓偑敪惗偟傑偡丅傑偨丄懝幐偼揹棳偺2忔偵斾椺偟傑偡偐傜丄椺偊偽1500V偒揹傪750V偒揹偱憲揹偡傞偲丄
摨偠弌椡傪憲傞応崌丄2攞偺揹棳偑棳傟傞偙偲偵側傝丄懝幐偼4攞偵側傞偙偲偵側傝傑偡丅偙偺柺偐傜戝梕検桝憲偺応崌偼偒揹揹埑傪崅偔偟偨曽偑桳棙偱偡丅
丂 壗曇惉偐偑摨偠曄揹強撪偵擖傞偺偱丄曄揹強梫検偑堦掕側傜丄揹埑崀壓偺尷搙傪挻偊側偄傛偆偵塣揮杮悢傪惂尷偡傞偐丄幵椉偺弌椡傪惂尷偡傞偐丄曄揹強偺娫妘傪嫹偔偡傞偐敾抐偑昁梫偵側傝傑偡丅
丂 彮検桝憲偺応崌偼丄偙傟傜偺栤戣傛傝寶愝旓傪梷偊傞柺偐傜600V乣750V戞嶰婳忦偒揹曽幃傪偲傞椺偑懡偄傛偆偱偡丅
丂 岎棳偒揹曽幃偱偼丄椡棪傗偒揹曽幃乮A俿摍乯偑棈傫偱偔傞偺偱扨弮偱偼側偄傛偆偱偡偑丄尨棟揑偵偼摨偠偲巚偭偰偄偄偲巚偄傑偡丅
嶕堷偵栠傞