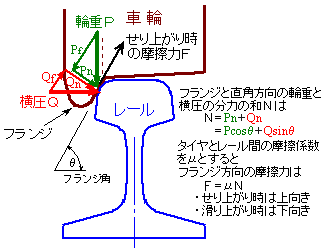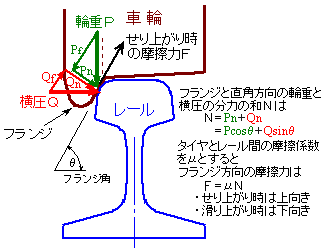8. 乗り上がり脱線とは? 営団日比谷線の事故の原因と対策は?
1. 乗り上がり脱線とは
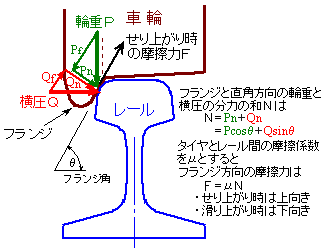
車両走行時にはレールには車両の重さが車輪を通じて垂直にかかっており、この車輪1輪にかかる垂直方向の荷重を輪重(P)と呼んでいます。この輪重Pは通勤電車の空車重量を26t、定員160名、混雑率180%とすると1両の重さが約44tになり、車輪は1両に2台車×4輪=8輪あるので停止した状態での輪重(静的輪重)は概ね5.5t程度になりますが、走行時は当然大きく変動しています。ある車輪が走行中に浮いて輪重が極端に小さくなることを輪重抜けといって 脱線の可能性が高くなり、一方極端に大きくなると著大輪重といって軌道に悪い影響を及ぼします。軌道の整備状況や、車両の重量、バネ下重量などが関係します。
カーブなどを走行するときには車輪のフランジがレール側面に接触して走行することが多く、右図のようにタイヤ踏面が浮いて釣り合った状態の時を考えます。
この時、輪重P、横圧Qともフランジとレールの接触している点にかかっていますが、横圧Qによりレールに押しつけられた車輪は回転に伴い接触点の摩擦力は
車輪を上に持ち上げるような方向に働くため、ある条件を満たすと回転しながらレール上にせり上がっていき、最悪の場合はレール上に乗り上げ脱線に至ることになります。
このようなことが起こらないためには、右図で
Pf≧Qf+F すなわち、Psinθ≧Qcosθ+μ(Pcosθ+Qsinθ)
の条件を満足する必要があります。μ=tanλとすると、この式から、
Q/P≦(tanθ-μ)/(1+μtanθ)=tan(θ-λ)
となります。このQ/P(キューバイピー)のことを脱線係数といい、フランジ角θが大きいほどQ/Pを大きくとれるので 脱線に対する安全性が高まります。在来線では60〜65度程度、新幹線では70度になっています。フランジの高さは30mm程度です。
μ=0.2と仮定してフランジ角65度の時のQ/Pを計算すると、1.36になります。この値P、Qの値はそれぞれ走行中常時変動するため 車両にこのPとQを連続的に測定できる特種な車軸(PQ軸)を組み込んで走行させて測定します。
2. 滑り上がり脱線とは
また、滑り上がり脱線という現象もあり、これは蛇行動のように比較的短時間に作用した横圧に押されて車輪が滑り上がる場合に起こり、脱線しないためには
Qf<Pf+F すなわち、Qcosθ<Psinθ+μ(Pcos+Qsinθ)
の条件を満足する必要があります。脱線係数でいうと
Q/P<(tanθ+μ)/(1-μtanθ)=tan(θ+λ)
となります。
3. 脱線係数の管理
脱線係数は鉄道の安全管理上大変重要な数値で、長い経験と実験等から安全をみて最大0.8以下になるように車両、軌道面で管理されているようです。
脱線係数は20分の1秒以下というような短い作用時間の場合は脱線に至る危険が小さいので作用時間に反比例して大きな値を許容しています。
4. 営団日比谷線03系8号車の脱線の原因は乗り上がり脱線と判明
運輸省の事故調査検討会が平成12年12月26日にまとめた最終報告「営団日比谷線中目黒駅構内列車脱線衝突事故に関する調査報告書」によると、
・ 脱線の形態は、急曲線部における低速走行時の「乗り上がり脱線」で、
・ 静止輪重のアンバランス、摩擦係数の増大、台車のばね特性、レール研削形状等の複数の因子の影響が複合的に積み重なったことによるもの
と推定しました。これらは、現地調査、事故に関係した軌道、車両の調査、試験車両による走行試験、車両運動シミュレーション等により得られたものです。
5. 事故調査検討会による再発防止策の提言
事故原因の分析結果等に基づき、同種の脱線事故再発防止に有効と考えられる次の5項目の対策が提言されました。
(1) 静止輪重の管理(アンバランスの管理値10%を努力目標とする)
(2) 軌道(平面性)の管理(未実施事業者について導入)
(3) レール研削形状の適正化
(4) 必要に応じ車輪フランジ角度の変更
(5) 脱線防止ガードの追加措置(推定脱線係数比が1.2未満の区間)
というものです。
ここで、「推定脱線係数比」という新しい概念が提言されました。これは
実際に車両が走行する際に発生していると考えられる脱線係数(車輪とレールとの間に作用する横方向と縦方向の力の比率)を、線路や車両の実際の諸元等の数値を用いてシミュレーション計算により算出したもの(推定脱線係数)に対して、車輪がレールから浮き上がり始めるときの脱線係数を理論的に算出したもの(限界脱線係数)が どの程度上回っているかを示す指標であり、この値が大きいほど、脱線に対しての余裕度が大きいと評価
するもので、推定脱線係数比が1未満であっても脱線に至までの行程には更に余裕があるため通常は脱線することは極めて少ないそうです。
今後、この提言に沿って各鉄道事業者が対策を進めることになっています。
索引に戻る