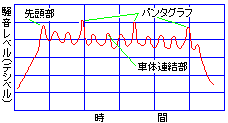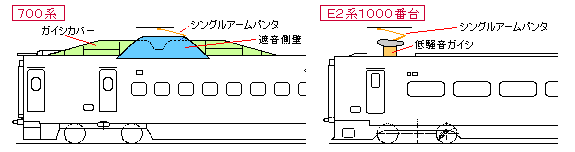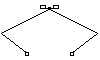
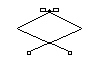
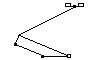
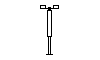
特徴等
・追随範囲を大きくとれる。
・低騒音で雪に強も強い。
・ピストンに送る圧力空気で押上力を制御する。
| 方 式 | 菱形 | 下枠交差形 | シングルアーム形 | 翼形 |
|---|---|---|---|---|
| 形 状 | 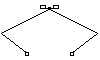 |
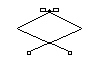 |
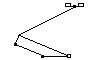 |
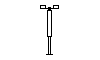 |
特徴等 |
・一般に使われている代表的な形。 ・追随範囲を大きくとれる。 |
・新幹線などに使われており、小形で屋根上スペースも小さくてすむ。 | ・最近新幹線、在来電車等に広く使われだした。今後の標準。 ・低騒音で雪に強も強い。 |
・JR西日本の500系新幹線用。 ・ピストンに送る圧力空気で押上力を制御する。 |
 パンタグラフはアルミや鋼管の骨組みの上部に架線と直接接触するすり板を載せた集電舟(舟体)を取り付けたもので、リンク機構とばねや空気シリンダで舟体が垂直に上下します。
架線と高速で接触しながら電気のやりとりを行うパンタグラフは、
パンタグラフはアルミや鋼管の骨組みの上部に架線と直接接触するすり板を載せた集電舟(舟体)を取り付けたもので、リンク機構とばねや空気シリンダで舟体が垂直に上下します。
架線と高速で接触しながら電気のやりとりを行うパンタグラフは、
| 菱形 | シングルアーム形 | シングルアーム形(新幹線) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
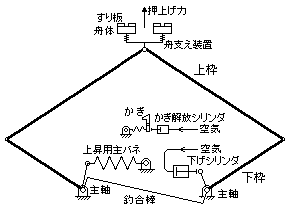 | 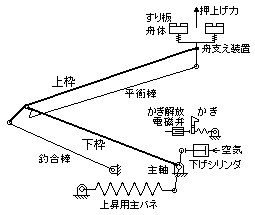 | 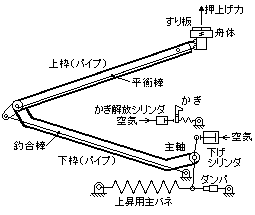 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
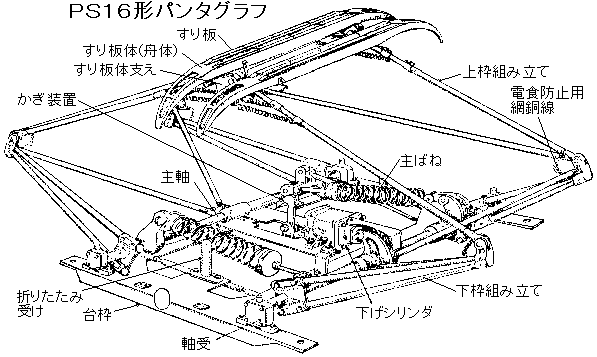
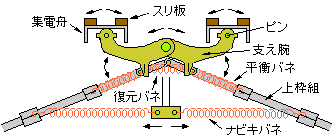
| 旧国鉄在来線用(PS16i) | 新幹線用(下枠交差) | 新幹線用(シングルアーム) |
|---|---|---|
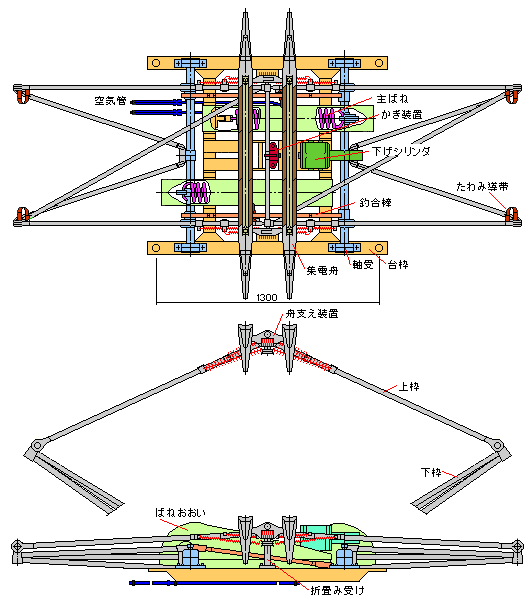 | 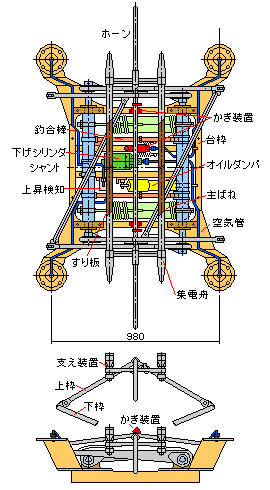 | 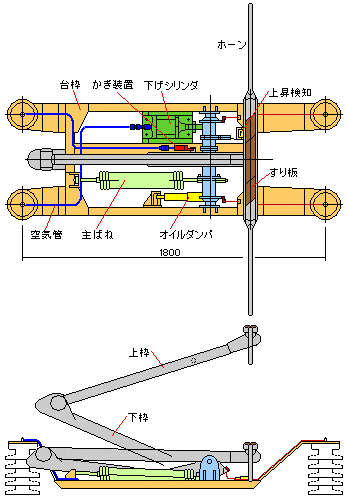 |
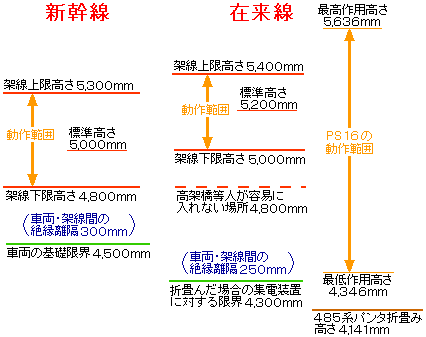 架線の高さは車体の高さだけでなく、在来線では踏切やこ線橋、トンネル等を考慮して決められますが、現在の標準は、右図のようになっています。いずれの数字もレール面上からの寸法です。特殊な場合はこれ以外の数字もあります。
架線の高さは車体の高さだけでなく、在来線では踏切やこ線橋、トンネル等を考慮して決められますが、現在の標準は、右図のようになっています。いずれの数字もレール面上からの寸法です。特殊な場合はこれ以外の数字もあります。
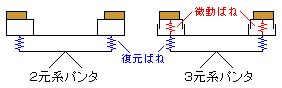
| パンタグラフ質点系モデル | 計算上の追随範囲 | 実際のパンタグラフの追随範囲 |
|---|---|---|
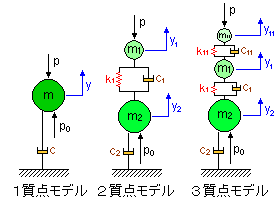 |
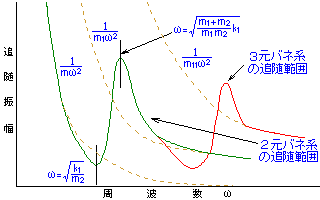 |
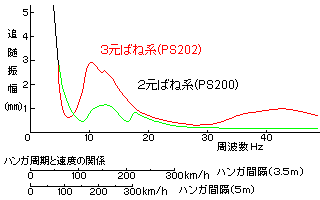 |
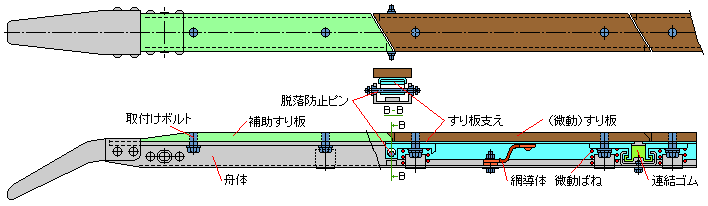
| 地域の類型 | 地域の概要 | 基準値 | 測定方法等 |
|---|---|---|---|
| i | 主として住居の用に供される地域 | 70デシベル以下 | 測定は、屋外において原則として地上1.2メートルの高さで行うものとし、 新幹線鉄道の上り及び下りの列車を合わせて、連続して通過する20本の列車について、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読み取って行うものとする。 |
| ii | 商工業の用に供される地域等ⅰ以外の地域であつて通常の生活を保全する必要がある地域 | 75デシベル以下 |