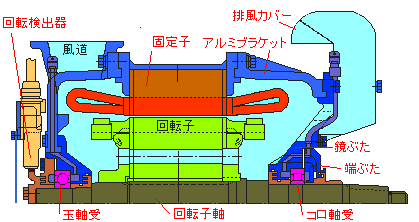
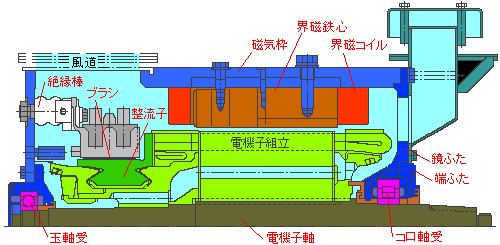
| 種別 | 誘導電動機(300kW) | 脈流直巻補極付き自己通風式直流電動機(230kW) |
|---|---|---|
| 断面 | 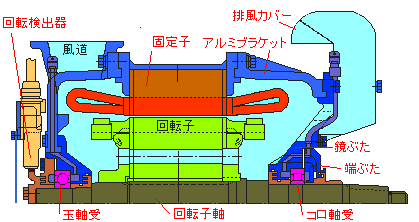 | 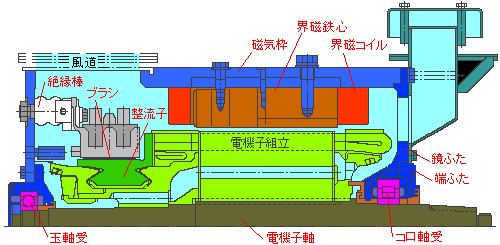 |
| 重量 | 300kW 450kg | 230kW 830kg |
| 種別 | 誘導電動機 | 直流電動機 |
|---|---|---|
| 断面 | 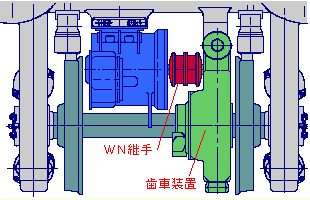 | 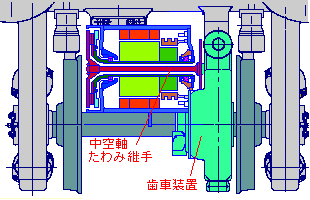 |
| 正位の状態 | 変位状態 |
|---|---|
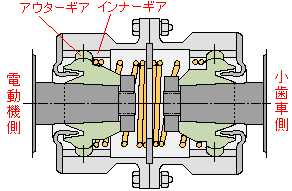 | 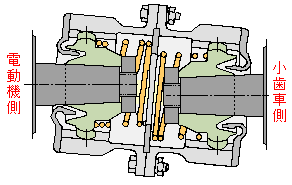 |
 | ここで、i:電流の瞬時値t:時間T:全運転時分 |
| 誘導電動機 | 直流電動機(直巻補極付) | |
|---|---|---|
| 原理 |
金属の円盤上で磁石を手で回してやると、磁石から出ている磁束と円盤導体の間の相対運動により起電力が誘導され(フレミング右手の法則)、図のような渦電流が流れます。 の電流と磁石の磁束とによって円盤は磁石の回転方向に力を受けて(フレミング左手の法則)回転します。 このとき、磁石と円盤とは必ず速度差があり、これを“すべり”といいます。 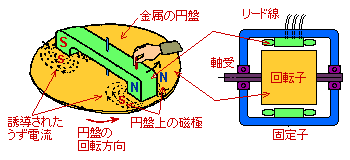 |
磁界内の導体に電流を流すと導体に力が働きます(フレミング左手の法則)。 電機子のコイルに電流を流すと、この法則によって力が働き、電機子が回転します。そして常に同じ方向の回転力を与えるためには半回転毎にコイルに流れる電流の向きを変えてやる必要があります。 この役目を持っているのが整流子です。 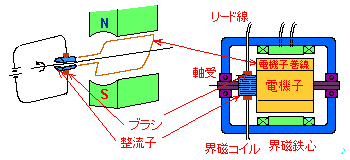 |
| 得失 |
|
|
| 特性式 | 3相固定子巻き線によって自動的に回転する磁界を作ることができます。 ここで、 V:インバータ出力電圧(電動機電源電圧) f n:回転数 Φ:磁束P:極数 I f T:トルク k:任意の定数 とすると、誘導電動機の特性は、次の式で表される。 n=120(f Φ=k・V/f I T=k・Φ・I これらから、 T=k・(V/f |
主電動機に端子電圧Etを与えると、界磁コイルと電機子に電流が流れます。界磁コイルによって磁束が生じ、この磁束と電機子電流によって回転します。 一方、この電流が磁束を切ることによって端子電圧とは反対方向の起電力(逆起電力)が発生します。 ここで、 Et:電動機端子電圧 Ec:電動機逆起電力 I:電機子電流 r:電機子の内部抵抗(小さい値) Φ:磁束 n:回転数 k:任意の定数 とすると、直流電動機の特性は、次の式で表されます。 I=(Et-Ec)/r Φ=k・I(磁路の飽和がないとき。飽和するとほぼ一定) n=(Et-I・r)/(k・Φ) Ec=k・Φ・n=Et-I・r≒Et T=k・Φ・I これらから、 n=Et/(k・I) T=k・I |
| 回路概要 | 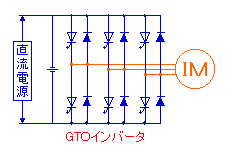 右図は、VVVFインバータ制御電動機の概念図で、インバータに使われるスイッチング素子はGTOサイリスタからより高速で廉価なIGBTになってきています。
右図は、VVVFインバータ制御電動機の概念図で、インバータに使われるスイッチング素子はGTOサイリスタからより高速で廉価なIGBTになってきています。更に低損失化等の改良が進められています。 |
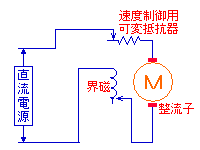 右図は、直流直巻電動機の概念図で、電機子と界磁が直列になっています。並列になった分巻形等も使われています。
右図は、直流直巻電動機の概念図で、電機子と界磁が直列になっています。並列になった分巻形等も使われています。電動機の電圧、電流制御には抵抗制御、直並列制御、チョッパ制御等が、界磁制御には界磁チョッパ、添加励磁制御等があります。 |
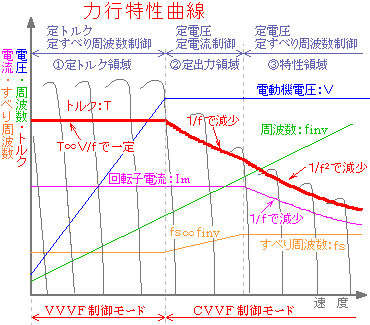 右図の特性曲線のように制御します。すべり率制御ですが、最近はベクトル制御が主流になっています。
右図の特性曲線のように制御します。すべり率制御ですが、最近はベクトル制御が主流になっています。| 東海道新幹線 | 山陽・東北・上越新幹線 | |
|---|---|---|
| 線路の急勾配 | 15‰以下 | 15‰以下 |
| 但し、延長2.5km以内18‰以下 延長1km以内20‰以下 | 但し、延長10km間平均勾配12‰以下 |
| 新幹線鉄道構造規則 | ||
|---|---|---|
| 線路の勾配 | 1 | 線路の最急勾配は、15‰以下とする。 但し、延長2.5km以内18‰以下、延長1km以内20‰以下 |
| 2 | 回送列車又は貨物列車のみを運転・・・(省略) | |
| 3 | 地形上等のため前2項の規定によることが困難である区間における最急勾配は、前2項の規定にかかわらず、列車の動力発生装置、動力伝達装置、走行装置及びブレーキ装置の性能を考慮して1000分の35とすることができる。 | |
| 4 | 列車の停止区域及び・・(省略)・・最急勾配は・・・1000分の3とする。 | |
| こう配は、車両の動力発生装置、ブレーキ装置の性能、運転速度等を考慮し、車両が起動し、所定の速度で連続して運転することができ、かつ、所定の距離で停止することができるものでなければならない。 | |
| 2 | 列車の停止区域のこう配は、車両の動力発生装置、ブレーキ装置の性能等を考慮し、列車の発着に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。 |
| 3 | 車両の留置又は解結をする区域におけるこう配は、車両が転動するおそれのないものとしなければならない。ただし、車両の転動を防止する措置を講ずる場合は、この限りでない。 |
| ①列車の走行区域における最急こう配は、次のとおりとする。 | |
| (ア) | 1000分の25とする。 |
| (イ) | 地形上等のため、前号によることが困難である区間においては、列車の動力発生装置、動力伝達装置、走行装置及びブレーキ装置の性能を考慮し、1000分の35とすることができる |
| ②列車の停止区域における最急こう配は1000分の3とする。 | |