| �S����49����2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@ | ���a50�N1��30�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���^�ǒ��a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �S���ēǒ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@ �n���S���̉Б�̊�ɂ��āA�ʎ��̂Ƃ����߂��̂ŁA���L�̎����ɗ��ӂ̏�A�lj��n���S�����Ǝ҂��w�����ꂽ���B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �S�y��9�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@ | ���a50�N2��14�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���^�ǓS�������a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �S���ēǖ��c�S�����y�ؓd�C�ے� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�n���S���̉Б�̊�̎戵���ɂ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�n���S���̉Б�̊�ɂ��ẮA���a50�N1��30���t���S����49����2�ɂ��ʒB���ꂽ���A���̎戵���y�щ��߂ɂ��Ă͉��L�̎����ɗ��ӂ̂����A�ʎ��ɂ�邱�ƂƂ��ꂽ���B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �i�ʁ@���j | ||||
| �n���S���̔r����̊ | ||||
| �@�n���S����v����ꍇ�̔r��������̂悤�ɒ�߂�B | ||||
| 1 | �p��̒�` | |||
| (1) | �Γ_�u���b�N | |||
| �@ | �@ | �@��ԉЂ����������ꍇ�ɁA��~��ɂ����ĉ����g�U�����Ԃ̂����A���Z�x���ł��Z���Ɛ��肳�����̋�Ԃ������B
�@�Γ_�u���b�N�̐ݒ�́A���ɂ��B | ||
| �@ | �@ | �A | �@���H���p�����̒f�ʂ́A�}�̂Ƃ���Ƃ��A�}�Ɏ����ȊO�̌`���̉w�\���ɂ��ẮA�}�Ɏ����l�����ɏ��������̂Ƃ���B | |
| �C | �@�f�ʐς́A���̊g�U����͈͂̒f�ʐς���ԗ��f�ʐρi�����������܂ށB�j�����������̂ŁA�}�̎ΐ��̕����Ƃ���B | |||
| �E | ���H���������́A20m�Ƃ���B | |||
| �G | �Γ_�u���b�N�̗e�ς́A�����ɂ��v�Z����B | |||
| �@ | �@ | �@ | �X���iAo�|Av�j�~ 20�@�@�@Ao���iVa�|Vm�j�^�k | |
| �@ | �@ | �@ | V | �F�@�Γ_�u���b�N�e�ρim3�j |
Ao | �F�@���H���p�����f�ʐρim2�j | |||
Av | �F�@�ԗ��f�ʐρi�����������܂ށB�j�im2�j | |||
Va | �F�@��~�ꕔ�̉Γ_�u���b�N�ݒ�f�ʂŁA�z�[���L���������̑S�e�ρim3�j | |||
Vm | �F�@Va���̒��A�K�i�������̊g�U���Ȃ������̗e�ρim3�j | |||
L | �F�@�z�[���L�����im�j | |||
| (2) | ���g�U�e�� | |||
| �@ | �@ | �@�R���R�[�X�K���ɂ����ĉЂ����������ꍇ�A�����g�U�����Ԃ̂����A�����ؗ�����Ɛ��肳����Ԃ̗e�ς������B
�@���g�U�e�ς̐ݒ�́A���ɂ��B | ||
| �@ | �@ | �A | �@�����́A�R���R�[�X�̓V�䍂������2m���������̂Ƃ���B | |
| �@ | �@ | �C | �@���ʐς́A�����̉��̊g�U���Ȃ������̖ʐς����������̂Ƃ��A�r���ݔ����ݒu����Ă���ꍇ�́A10���Ԃ̗ݐϊ��C�ʂ�V�䍂���ŏ��������̂����ʐςɉ�������̂Ƃ���B | |
| �@ | �@ | �E | �@���g�U�e�ς́A�����ɂ��v�Z����B | |
| �@ | �@ | �@ | �@Vo���iAf�|At�{Vs�^H�j �~ �iH�|2�j | |
| �@ | �@ | �@ | Vo | �F�@���g�U�e�ρim3�j |
Af | �F�@�R���R�[�X�K�����ʐρim2�j | |||
At | �F�@�R���R�[�X�K���̒����̉��̊g�U���Ȃ������̖ʐρim2�j | |||
Vs | �F�@�r���ݔ���10���Ԃ̗ݐϊ��C�ʁim3�j | |||
H | �F�@�R���R�[�X�K���̓V�䍂���im�j | |||
| 2 | ��~��K���̔r���� | |||
| (1) | �r���ݔ��̕K�v���C�\�� | |||
| �@ | �@ | �@��~��ɑ���r���ݔ��̊��C�\�͂́A�����Ƃ��āA�Γ_�u���b�N�e�ς̑傫�����ƂɁA�ʕ\�ɋK�肷�銷�C���m�ۂ�����̂Ƃ���B | ||
| �@ | (2) | �r������ | ||
| �@ | �@ | �@�r�������́A��1�̔��ꏊ�ƂȂ�R���R�[�X�K���ɘA������K�i���ɂ́A���~�C��������铙�A�R���R�[�X�K���ɉ����g�U����̂�}���ł�������Ƃ�����̂Ƃ���B | ||
| 3 | �R���R�[�X�K���̉��� | |||
| �@ | (1) | �K�v���g�U�e�� | ||
| �@ | �@ | �@�R���R�[�X�K���́A�����Ƃ���1,050m3�ȏ�̉��g�U�e�ς��m�ۂ�����̂Ƃ���B | ||
| �@ | (2) | �w�ݔ��̍\���� | ||
| �@ | �@ | �@�R���R�[�X�K���̉Д������ɂ́A��~��K���ւ̉��̊g�U��}���ł���\���Ƃ�����̂Ƃ���B | ||
| �@ | (3) | �抷����K�͉w | ||
| �@ | �@ | �@�R���R�[�X�K���̉���́A�w�Ƒ����̉w�i����̏�~����g�p������̂������B�j�Ƃ̋�悲�ƂɁA��L�̊��������̂Ƃ���B | ||
| 4 | �����̔r���ݔ� | |||
| �@ | �@�����ɂ́A�r���@��݂�����̂Ƃ���B�r���@�́A�r�����̊J���ɔ��������I�ɍ쓮���A���A 1���ԂɁA120m3�ȏ�ŁA���A�h����敔���̏��ʐ�1m2�ɂ�1m3�i2�ȏ�̖h����敔���ɌW��r���@�ɂ����ẮA���Y�h����敔���̂������ʐς̍ő�̂��̂̏��ʐ� 1m2�ɂ�2m3�j�ȏ�̋�C��r�o����\�͂�L������̂Ƃ���B���̑��\�����ɂ��ẮA���z��@�{�s�ߑ�126���� 3�̋K��ɏ�������̂Ƃ���B | |||
| 5 | �w�����̑Ή��� | |||
| �@ | �@�Д������̉w���������A�����ݔ���K�m�ɑ���ł���悤�ɂ���ƂƂ��ɁA���q�̔��U����K�ɍs�����Ƃ��ł���悤����E�P���̎��{���A�ً}���̑̐���������̂Ƃ���B | |||
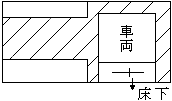
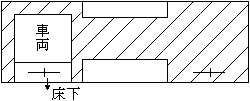
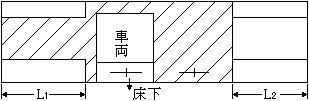
| �i�l�����j | �@�З�ԂƔ��Α��̃z�[���́A�O���������V�䂪�Ⴂ���߉��͊g�U�����A�אڃz�[����y�ыO�����ɂ̂݊g�U������̂Ƃ��A��������З�Ԃɂ��ݒ肳���f�ʂ̂������Ȃ�f�ʂƂ���B
�i��F�}�ɂ����āA�z�[������L1��L2�̏ꍇ�A�ΐ��̕�����ݒ�͈͂Ƃ���B�j |
| �Γ_�u���b�N�e��m3 | 1���ԓ��� �K�v���C�� | �Γ_�u���b�N�e��m3 | 1���ԓ��� �K�v���C�� |
| 255�ȉ� | 50 | 446�@�`�@460 | 27 |
| 256�@�`�@260 | 49 | 461�@�`�@476 | 26 |
| 261�@�`�@266 | 48 | 477�@�`�@492 | 25 |
| 267�@�`�@271 | 47 | 493�@�`�@509 | 24 |
| 272�@�`�@277 | 46 | 510�@�`�@528 | 23 |
| 278�@�`�@283 | 45 | 529�@�`�@547 | 22 |
| 284�@�`�@290 | 44 | 548�@�`�@568 | 21 |
| 291�@�`�@296 | 43 | 569�@�`�@590 | 20 |
| 297�@�`�@303 | 42 | 591�@�`�@613 | 19 |
| 304�@�`�@311 | 41 | 614�@�`�@638 | 18 |
| 312�@�`�@318 | 40 | 639�@�`�@665 | 17 |
| 319�@�`�@326 | 39 | 666�@�`�@693 | 16 |
| 327�@�`�@335 | 38 | 694�@�`�@723 | 15 |
| 336�@�`�@343 | 37 | 724�@�`�@756 | 14 |
| 344�@�`�@353 | 36 | 757�@�`�@790 | 13 |
| 354�@�`�@362 | 35 | 791�@�`�@827 | 12 |
| 363�@�`�@372 | 34 | 828�@�`�@868 | 11 |
| 373�@�`�@383 | 33 | 869�@�`�@909 | 10 |
| 384�@�`�@394 | 32 | 910�@�`�@955 | 9 |
| 395�@�`�@406 | 31 | 956�@�` 1005 | 8 |
| 407�@�`�@418 | 30 | 1006�@�` 1056 | 7 |
| 419�@�`�@432 | 29 | 1057�@�` 1113 | 6 |
| 433�@�`�@445 | 28 | 1114�ȏ� | 5 |