朝の通勤時間帯で満員状態の西成線(現在のJR西日本桜島線)安治川口駅に到着進入中のキハ42000型(後のキハ04型)ガソリン動車(3両編成)が分岐器上通過中に途中転換し、最後尾車の後位台車が異線進入し脱線・転覆し、燃料のガソリンに引火して通勤客等死亡181名・負傷92名の戦前最大の鉄道死亡事故となった。
原因は同駅信号掛が後隣駅で待機中の続行列車の発車を急ぎ、当該列車の分岐器通過完了を確認しないまま転轍した事による。
3両編成の普通1452列車が生駒山トンネルの東入口から550m進入したとき、先頭車の主抵抗器が加熱して出火、列車は停止した。
先頭車の乗客はトンネル西口に向かって無事避難したが、後部2両の乗客はトンネル東口に避難したところ西風に煽られた煙に巻かれる等で多くの死傷者がでた。半鋼製の車両は3両とも焼損した。
午後1時38分頃、吊り架線ガイシ取替作業中誤ってスパナをビームに接触させたため地落し吊り架線が切断、一端が垂れ下がってレールに接触、地気したため横浜変電区と鶴見き電室の高速度しゃ断機が動作した。
再送電した際、吊り架線はレールから離れ250〜300mm垂れ下がった状態になっていたため、しゃ断機は動作せず、き電的には正常なものとなった。
午後1時42分頃、桜木町終着のモハ63形南行電車(5両編成)がここを通過する際、屋根上に大きな火花が発生したので非常ブレーキをかけパンタグラフを下げようとしたが、先頭パンタグラフがこの垂下した架線に絡み付いて横倒しになり、車体と短絡(ショート)、火花が発生し続け、屋根から車体に火災が拡大していった。
この時、横浜変電区のしゃ断機は動作したが鶴見き電室のものは動作せず48分に局からの停電指令が出るまで1500Vの電流が数分間流れ続けた。
屋根上で発生した火は瞬時にして180名ほどが乗っていた1両目の車両を猛火に包み、発火から10分ほどで全焼、2両目にも延焼してこれを半焼したが、午後2時頃消防作業により鎮火した。
モハ63は戦中の昭和19年に登場した通勤型電車で、木材が多用されていたため火の回りが早く、また、停電による側扉開不能、窓は硝子節約のため中段の開かない3段窓(1段約30cm)、車両は1両毎に区切られていて貫通路がなく、車端扉は手前に開ける内開戸で1両目は桜木町駅の改札口に一番近く満員だったこともあり開けられない状態だったこと等から 窓からかろうじて脱出した人以外の多くの人が犠牲になった。
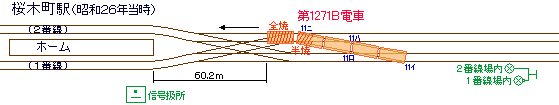
午後2時16分頃、3両編成の急行4402電車が高野線紀伊神谷駅出発後、回生ブレーキで運転中に先頭車のモハ1283号車の主抵抗付近から出火、同時に190人の乗客は大混乱になり乗務員等の制止にもかかわらず窓ガラスを破損して車外に脱出しようとしたため、18号トンネル内に停車した。
乗務員は保線作業員等の協力で旅客の避難誘導、消火器による消火に当たったが3両とも全焼、事故のショックから1名が死亡、避難時の混乱から42名が負傷した。
回路しゃ断機の故障によって主抵抗器が加熱し地気したため出火したもので、電車の骨組みは鋼製だったが屋根、床、内装は木製だった。
11時35分頃、中目黒行きの東武鉄道所属の日比谷線6両編成(6M)01T電車の営団運転士が茅場町駅手前で制御関係に異常を感じ、連絡を受けて広尾駅で待機していた検車係が 乗車、中目黒駅に到着した12時頃に3両目配電盤の第2ユニットの制御回路を解放した。
北春日部への折り返し運転中、たまたま乗車していた駅務員が3号車床下に異音があるのを気づき、広尾で点検した結果、第3制輪子が加熱していたので第2制動筒を解放して運転 を継続した。
六本木駅で車掌が客扱い中に3両目の床下から発煙しているのを認め、点検した結果、主抵抗器が赤熱しているのを認めたが、制輪子の圧着と考え第1台車を解放、営業運転継続不能と判断し旅客を降車させ霞ヶ関駅の測線へ回送運転を始めたところ、途中異常に速度が落ち、六本木-神谷町の上り勾配を力行運転中に運転不能となって12時39分自然停車した。
このとき、電車の後方から激しく発煙していたので自力走行不能と考え救援列車を要請、指令は了承し停電を手配、運転士はパンタグラフ下げ押しボタンを操作し、再送電を要請、点検等のために降車した。13時6分頃六本木で乗客を降ろした後続電車と併結し、発車しようとしたが3号車主回路の地落によって変電所しゃ断機が動作、その後送電不能となった。パンタの状況を確認したところ、故障車の2両目のパンタが上がっていたので人力で降下させたが他は煙のために確認できず、前途運転不能と認め乗務員は手歯止め、指令へ連絡の上全員待避した。
地下鉄通風口から煙が噴出しているという通報を受けた東京消防庁は12時54分に消防隊の出動を命じ、13時30分頃から神谷町駅と六本木駅から進入して乗務員の救援、消火活動を行い、3両目は全焼、他の1両は半焼したが14時53分鎮火した。
原因は、第2ユニットの制御回路が故障し、主回路が力行並列段で停止し、そのまま折返し前に制御回路を解放したため、折返し運転時に運転士が転換器を操作しても第2ユニットの極性が変わらず主電動機が発電機の発電ブレーキ状態となり、主抵抗器が過熱、上部の配線が燃焼し延焼していった。
この火災においては、火災発生場所が駅と駅との中間であったため、出火車両との連絡ができず、火源確認に時間を要した。また消防隊が使用していた自給式呼吸器はせいぜい30分くらいしか使用できないものであり、その数も限られていたため、神谷町駅からは進入できず、消防隊の進入口を確保するのに時間を要した。この火災後、東京消防庁では、地下鉄内での空気流を調査し、地下鉄火災時の進入口についての検討を行った。
(旅客約760名 職員13名 食堂車従事員8名 郵政省職員9名乗車)
午前1時10分頃、大阪発青森行急行501列車「きたぐに」(EF7062機牽引・現車15両)が、北陸本線敦賀−南今庄間の「北陸トンネル」(長さ13km870m)の上り勾配を約60km/hで走行中に前から11両目の食堂車(オシ17型)附近から 火災が発生していると旅客から通報を受け、乗務員が消火に努めると同時に車掌弁で停止手配、同時に機関士と連絡、列車は13分頃車両の車掌弁と機関士の操作によって敦賀寄りの入口から約5.3km入ったトンネル内で非常停止した。
列車防護、駅への連絡を行いながら乗務員、食堂従業員、添乗公安等が消火に努めたが、発煙がひどくて消火の見通しが得られなくなったため食堂車の切り離し作業に移り、11両目と12両目を約60m切り離し、次いで10両目と11両目の切り離し中、下り線が52分頃架線停電(漏水案内用トイが架線に接触?)したため運転が不能となった。
このため、乗客の避難誘導に努めるとともに連絡を受けた関係機関が救援に当たったが、トンネル内に充満した煙や混乱のため救出活動は難航し、30名(内1名は指導機関士)が死亡し、714名が負傷した。
深夜で敦賀発車直後だった為に編成後部の座席車の乗客は脱出したが前部の寝台の乗客は睡眠中であり、避難が遅れたところに火災で発生した有毒ガスがトンネル内に充満し、この ために負傷者が714名にも広がり、死傷者総計で日本の鉄道事故最悪の大惨事となった。
上り「急行立山3号」は木の芽信号場の停止信号で1時31分頃停止、敦賀駅と連絡中に501列車から敦賀駅への救援要請を傍受、信号が青になったので300mほど進行したところで人影を認め停止、避難してきた人約400人を乗せて今庄駅に退行した。
当時、急行用在来型一般車の淘汰用として軽量化された10系客車が多数運用されていたが、軽量化の為に合成樹脂や合板を多用していた事が有毒ガスの発生を招いている。また長大トンネルの真ん中で停止した列車から徒歩で乗客が避難するには時間がかかり過ぎ、換気装置も無かった事などから災害の被害が拡大している。
11時35分頃までに旅客、職員の救出が完了、長時間高温にさらされて構体が残るのみとなったオシ17型客車を含む501列車は12時43分に敦賀、今庄駅に収容され、その後現場検証を経て22時45分に上下線とも開通した。
火災原因は食堂車喫煙室長椅子下の暖房器配線の漏電により金原現象を起こしたことと暖房機配線の取付弛みによる異常発熱が競合して出火したものと推定されている。
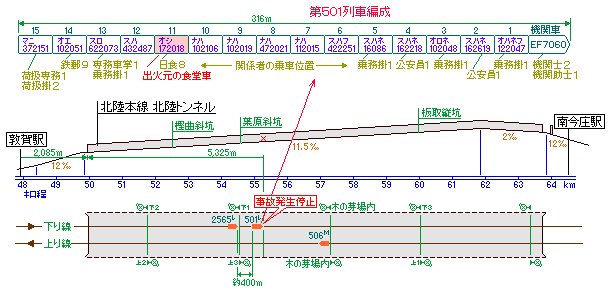
日比谷線営団3000形8両編成(8M)B671S電車が恵比寿駅を定時発車、広尾駅手前800mを力行運転中、7時3分に過負荷継電器が動作(乗客がボーンという音を聞いている)、停電となり、再送電を待ってノッチを投入しても加速しないので惰行運転を行い同6分に広尾駅に到着。
旅客全員を降車させ、最後部運転台で起動試験を行ったところ、起動可能であった。乗客から床下から少し煙が出ていると知らされたので点検したが異常は認められず、第5車両(前から4両目)の制御回路を開放して推進で同駅側線に21分に留置したが、その際同車両から発煙しているのが認められた。
パンタグラフを降下して点検中、第5車両の断流機付近と判明したので、消火器で消火を始めたが、大きな音がして発煙が激しくなり、27本の消火器(粉末)を使ったが消火効果がなくなったので40分に待避した。
発煙が収まらないので8時20分に消防に連絡、5分後消防車が到着し35分から放水開始、42分鎮火した。このため、5両目3539号車の断流器焼損、高圧ツナギ箱等の床下機器を一部焼損した。
原因は、出火車の断流器のアーク・オーバにより断流器内で発火、ゆっくり拡大し、7時40分にガス爆発を起こし断硫機のカバーが変形したことにより燃焼が激しくなったものと考えられている。
高崎から長岡に向かうJR東日本新潟支社の団体専用3両編成欧風気動車「アルカディア(キロ59-508(キハ58-626) キロ29−505(キハ28−2010) キロ59-509(キハ58−650) )3両編成」が上越線土樽駅を越えて松山トンネルを通過中に、18時03分頃最後部の1号車のキハ58を改造したキロ59−508床下から出火、走行中、乗務員は1号車の乗客を2号車へ誘導し、消火活動につとめた。
運転士は消火活動を考えて有人の越後湯沢駅までそのまま走行しようとしたが、煙が車内に充満してきたので乗客避難、消火のため越後中里−岩原スキー場前間の大きく左にカーブしている地点に緊急停車した。
消火器による消火に努めたが、最後部車両の消音器内部から発火して煙突を溶損させ、最後部1両客室内部は全焼した。
列車無線を通じて消防署への要請もしてあったので消防車が到着、消火にあたるも火の勢いは収まらなかったが、他の車両への延焼は免れている。
この火災事故により、「アルカディア」は登場後わずか一年で事実上引退へと追い込まれ、残されたキロ29-505とキロ59-509の2両は盛岡で新たに1両を加え再改造され、「 kkenji」となった。