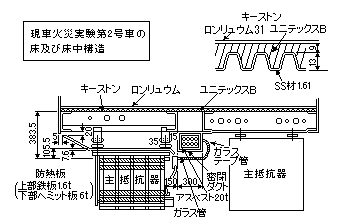温度15℃〜30℃
湿度60%〜75%
で空気の流動はない状態とする。
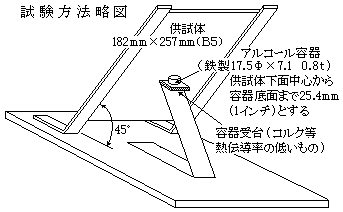
電車の火災事故対策について
| 鉄運第81号 | |||||||||||||||||||||
| 昭和44年5月15日 | |||||||||||||||||||||
| 陸運局長殿 | |||||||||||||||||||||
| 鉄道監督局長 | |||||||||||||||||||||
| 電車の火災事故対策について下記のとおり定めたので、これにより管下事業者を指導されたい。なお、次の通達は廃止する。 | |||||||||||||||||||||
| 昭和31年6月15日付け鉄運第39号「電車の火災事故対策について」 昭和31年8月6日付け鉄運第58号「電車の火災事故対策の通達に関する補足説明について」 昭和32年1月25日付け鉄運第5号「電車の火災事故対策に関する処理方について」 昭和32年1月25日付け鉄道第6号「電車の火災事故対策に関する処理方の注釈について」 昭和32年12月18日付け鉄運第136号「電車の火災事故対策に関する処理方の一部改正について」 昭和32年12月18日付け鉄道第137号「電車の火災事故対策に関する処理方の一部改正に伴う注釈について」 | |||||||||||||||||||||
| 記 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 項 目 | 要 項 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 般 |
| |||||||||||||||||||||
| 車体構造 | 屋 根 |
| ||||||||||||||||||||
| 外板、 天井及び 内張り | 金属等不燃性のものとし、これに表面塗装をした場合も不燃性のものとすること。 | |||||||||||||||||||||
| 床 |
| |||||||||||||||||||||
| 断熱材 及び 防音材 | ガラス繊維、石綿等不燃性のものとすること。 | |||||||||||||||||||||
| 座 席 | 表地、詰物包及び詰物は、難燃性のものとすること。 | |||||||||||||||||||||
| 日除け 及び幌 | 難燃性のものとすること。 | |||||||||||||||||||||
| 貫 通 路 |
| |||||||||||||||||||||
| 主回路及び電孤、電 熱発生機器の防護等 |
| |||||||||||||||||||||
| 予 備 灯 | 客室内には、常用室内灯が消灯したときは自動的に点灯する予備灯を設けること。 | |||||||||||||||||||||
| 放送装置及び 通話装置 |
| |||||||||||||||||||||
| 自動戸閉装置の 操作装置 | 自動戸閉装置の操作装置は、停電の際にも開扉できるものであること。 | |||||||||||||||||||||
| 非常措置の標示 |
| |||||||||||||||||||||
| 消 火 器 |
| |||||||||||||||||||||
| そ の 他 |
| |||||||||||||||||||||
別表2 A基準
| 項 目 | 要 項 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車体構造 | 屋 根 |
| ||||||||||
| 外板、天井 及び内張り | 金属等不燃性のもの(金属等不燃性のものによりだき合わせた構造のものを含む。)とし、これに表面塗装した場合も不燃性のものとすること。ただし妻部の外板は、難燃性のものとすることができる。 | |||||||||||
| 床 |
|
|||||||||||
| 座 席 | 表地は、つとめて難燃性のものとすること。 | |||||||||||
| 貫 通 路 |
| |||||||||||
| 主回路及び電孤、電 熱発生機器の防護等 |
| |||||||||||
| 予 備 灯 | 客室内には、常用室内灯が消灯したときは自動的に点灯する予備灯を設けること。 | |||||||||||
| 放 送 装 置 | 車掌から客室内へ放送できる装置を設けること。 | |||||||||||
| 非常措置の標示 |
| |||||||||||
| 消 火 器 |
| |||||||||||
別表3 B基準
| 項 目 | 要 項 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車体構造 | 天井及び外板 | 金属等不燃性のものとすること。ただし、妻部の外板は難燃性(不燃性、極難燃性を含む。以下同じ。)のものとすることができる。 | ||||||
| 床 | 電弧又は電熱を発生する機器の上部の床下面には、金属等不燃性の板を張ること。 | |||||||
| 貫 通 路 |
| |||||||
| 主回路及び電孤、電熱発生機器の防護等 |
| |||||||
| 予 備 灯 | 客室内には、常用室内灯が消灯したときは自動的に点灯する予備灯を設けること。 | |||||||
| 非常措置の標示 |
| |||||||
| 消 火 器 |
| |||||||
| 区分 | アルコール燃焼中 | アルコール燃焼後 | ||||||
| 着火 | 着炎 | 煙 | 火 勢 | 残炎 | 残じん | 炭 化 | 変 形 | |
| 不燃性 | な し | な し | 僅 少 | - | - | - | 100mm以下の変色 | 100mm以下の表面的変形 |
| 極難燃性 | な し | な し | 少ない | - | - | - | 試験片の上端に達しない | 150mm以下の変形 |
| あ り | あ り | 少ない | 弱い | な し | な し | 30mm以下 | ||
| 難燃性 | あ り | あ り | 普 通 | 炎が試験片の上端を超えない | な し | な し | 試験片の上端に達する | 縁に達する変形、局部的貫通孔 |
| (注) | 1 | 炭化、変形の寸法は、長径で表わす。 |
| 2 | 異常発炎するものは区分を1段下げる。 | |
| 3 | 判定については次の試験方法による。 |
| 試験方法 | ||
| 鉄道車両用非金属材料の試験方法は、図に示すとおりB5判の供試材(182mm×257mm)を45°傾斜に保持し、燃料容器の底の中心が、供試材の下面中心の垂直下方25.4mm(1インチ) のところにくるように、コルクのような熱伝導率の低い材料の台にのせ、純エチルアルコール0.5ccを入れて着火し、燃料が燃えつきるまで放置する。 | ||
| 燃焼性判定は、アルコールの燃焼中と燃焼後とに分けて、燃焼中は供試材への着火、着炎、発煙状態、炎の状態等を観察し、燃焼後は、残炎、残じん、炭化、変形状態を調査する。 | ||
| 供試体の試験前処理は、吸湿性材料の場合、所定寸法に仕上げたものを通気性のある室内で直射日光を避け床面から1m以上離し、5日以上経過させる。 | ||
| 試験室内の条件は 温度15℃〜30℃ 湿度60%〜75% で空気の流動はない状態とする。 | ||
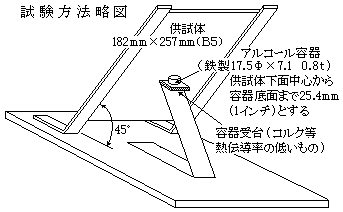 | ||
| 鉄運第81号の2 | |
| 昭和44年5月15日 | |
| 陸運局長殿 | |
| 鉄道監督局長 | |
| 電車の火災事故対策については、昭和44年5月15日付け鉄運第81号で通達したが、同通達中第 1項の「別に指定する路線」として、次のとおり指定する。 | |
| 1 懸垂式鉄道の路線 2 跨座式鉄道の路線 3 案内式鉄道の路線 | |
| 鉄運第82号 | |
| 昭和44年5月27日 | |
| 運輸局鉄道部長殿 | |
| 鉄道監督局民営鉄道部 運輸車両課長 | |
| 電車の火災事故対策については、昭和44年5月15日付け鉄運第81号及び第81号の2により通達されたが、この取扱い及 び解釈については、下記によることとされたい。 | |
記 | |
| 1〜1 | 地方鉄道及び軌道の路線を運転する車両に適用する。 ただし、軌道運転規則を適用する路線を運転する車両及び低床式車両は、構造上適用しがたい事項を除き事業者が自主的にこの基準に適合させるものとする。 なお、日本国有鉄道の車両が乗入運転により、この通達の適用を受けることとなる場合は、乗入れの認可に際し、この基準への適合について確認することとする。 |
| 1〜2 | 通達本文記第1項の「地下線」とは、地下式構造(車両定規と建築定規の間隔が、側部において400ミリメートル末満のもの)のものをいう。 |
| 1〜3 | 通達本文記第2項の「長いトンネル」とは、始終端駅に地下乗入れするトンネルを含め、山岳トンネル(山岳地帯に設けられるトンネルをいう。以下同じ。)にあっては延長2キロメートル、都市トンネル(市街地の地下に設けられるトンネルをいう。以下同じ。) にあっては延長1.5キロメートルを越えるトンネル及び延長がそれぞれ前記以下であって、トンネル内の駅間(ホーム端間)距離又はトンネル端と最寄駅ホーム端間の距離が1キロメートルを越えるものをいう。「短いトンネル」とは、山岳トンネルにあっては延長1キロメートル、都市トンネルにあっては750メートル以下のものをいう。 |
| 1〜4 | 前項の場合、トンネル内で折返し運転のみをする車両については、その折返し駅をもって始終端駅とみなす。 |
| 1〜5 | 削除 |
| 1〜6 | 「今後新製されるもの」とは、全く新たに製作される車両をいい、他社等から譲り受け、これについて車両設計認可申請をするもの等は合まない。 |
| 1〜7 | 通達本文記第2項及び第3項の今後新造されるものについては、事業者が自主的にそれぞれ「A-A基準」及 び 「A基準」に適合させることを期待するものであるが、第2項のものについては、少なくとも異常閉回路防止装置を設けるように指導すること。 |
| 1〜8 | 通達本文記第4項の各事業者ごとの既存車両の改造工事計画については、工事内容、工事能力、車両数、予備車等を検討し、できるだけ早期に工事を完了させるよう指導すること。 |
| 1〜9 | 車両設計認可及び車両設計変更認可の申請にあたっては、この基準への適合について、別紙1の要領によって記述させること。 |
| 1〜10 | 通達本文記第5頂の「鉄道車両用材料の燃焼性規格」への適合判定は、 当分の間、交通安全公害研究所鉄道研究室において行うものとし、その試験依頼等の手続きは、別紙2によること。 |
| 1〜11 | 車両の異常事態が生じた生じた場合の措置については、旅客の避難誘導について、その時期を失わないよう特に留意して、予めその手順等を各社ごとに定めさせ、十分に訓練を行なうよう指導すること。 |
| 2〜1 | 「屋根」とは、雨樋(雨樋のないものは雨切り)より上をいう。 |
| 2〜2 | 「露出金具」とは、屋根上の機器箱、通風器、歩み板、同取付金具、昇降用握り金具等をいう。 |
| 2〜3 | 「外板、天井及び内張り」の「金属等不燃性のもの」とは、金属のほか不燃性の材料とすることができることを意味する。 |
| 2〜4 | 「床」の「詰物」とは、ユニテックス等キーストン構造の床に詰めるものをいうが、ハードボード、耐水ベニア等を金属と金属の間又は金属と床敷物の間に狭んだものも「詰物」と解する。 (注)現車火災試験における第2号車の床及び床下構造は、別紙3のとおりである。 |
| 2〜5 | 「座席」には、背すりを合むものとする。 |
| 2〜6 | 連結した側の貫通路扉が開き戸である場合は、その扉は解放しておくこと。 |
| 2〜7 | 貫通路には幌を設けるのを原則とするが、列車の運行途中において解結する箇所は、手すり等幌以外のものでもよい。この場合は、前項の扉を含め、非常の場合には通行してもよい旨を表示し、かつ、旅客が容易に開く ことができる状態にして、貫通路扉は閉じておくこと。 |
| 2〜8 | 「異常な閉回路を構成しない構造」とは、制御器の故障等により、カム軸が途中停止し、正規の閉回路以外の閉回路ができたときは、その異常な閉回路を開くスィッチを有することを原則とする。ただし、既存車であって、逆転器が正規の方向に転換していないときは列車が起動できない構造となっているものは、上記のスイッチを設けたものと同等とみなす。 |
| 2〜9 | 「主回路抵抗器」とは、主回路内の抵抗器のうち、減流抵抗器、起動抵抗器、制御抵抗器、誘導分路抵抗器等比較的発熱量の大きいものをいい、電圧計、空転防止装置等の抵抗器は含まない。 |
| 2〜10 | 屋根上の主回路抵抗器についての周辺の配線禁止、配線の金属防護及び防熱板については、この基準により難いので、つとめてこれに準じた構造とすること。 |
| 2〜11 | 強制通風冷却式の主回路抵抗器の配線禁止、配線の金属防護及び防熱板については、通風ダタト内を配線禁止(主回路抵抗器の配線を除く。)範囲とし、吹出口の附近の熱風の当る部分の配線は極力さけ、やむをえないものは金属防護をするほか、床下の塩化ビニル製電線管の使用は極力さけるものとし、防熱板は必要としない。 |
| 2〜12 | 「耐熱性の被覆」とは、ポリクロロプレン、ポリフレックス、シリコン等比較約熱に強いものをいい、塩化ビニルは含まないものとする。 |
| 2〜13 | 電線の金属防護をする場合、既存車であって塩化ビニル製電線管を使用しているものは、その上に更に金属管又は密閉ダクトで覆う方法でよいが、更新i時には塩化ビニル製電線管を除き、金属管又は密閉ダクトのみで防護する方法に改めること。 |
| 2〜14 | 防熱板の形状については、別紙3の実験車の例を参考として床下機器の配置に応じて考慮すべきである。 |
| 2〜15 | 「予備灯」は、1車両につき10ワット×4個相当のものが、扉は片側開放、誘導無線は受信状態としたまま、少なくとも30分程度の連続点灯ができることが望ましい。 |
| 2〜16 | 「非常措置の標示」は、その位置、大きさ、色等について、満員状態においても、その周辺の相当数の旅客の目に付きやすいよう考慮すること。 |
| 2〜17〜1 | 「消火栓」は、乗務員室及 び客室外に設けるものは、一塩化一臭化メタンのものでもよいが、その取扱いについては乗務員に十分教育してお くこと。 |
| 2〜17〜2 | 客室内に設けるものは、粉末、強化液等無害のものとし、四塩化炭素 、一塩化一臭化メタン、ニ臭化四弗化エタンのものはさけること。 |
| 2〜17〜3 | 消火能力の小さいものを複数で設けてもよい。 |
| 3〜1 | 「屋根」については2〜1によること。 |
| 3〜2 | 「露出金具」については2〜2によること。 |
| 3〜3 | 「外板、天井及び内張り」の「金属等不燃性のもの」については2〜3によること。 |
| 3〜4 | 「外板、天井及び内張り」の要領中「ただし書」は、FRP等の妻外板への使用を認めたものである。この場合、妻外板と一体となったものは、屋根の一部にまで及んでもよい。 |
| 3〜5 | 床下面の金属板は、床下面に密着していなくてもよいが、床下の熱風が床下面に影響を与えないよう、金属板の位置、取付方法に留意すること。 |
| 3〜6 | 「座席」については2〜5によること。なお、「つとめて難燃性としたのは、可燃性のものでもよい意味ではなく、燃焼性試験の結果、極く僅かな差で難燃性に適合しないものがあるので、これを考慮したものである。 |
| 3〜7 | 「貫通路」については2〜6及 び2〜7によること。 |
| 3〜8 | 「主回路抵抗器」については、2〜9、2〜10、2〜11及び2〜13によること。 |
| 3〜9 | 「防熱板」の形状については2〜14によること。 |
| 3〜10 | 「予備灯」については2〜15によること。 |
| 3〜11 | 「非常装置の標示」については2〜16によること。 |
| 3〜12 | 「消火器」については2〜17によること。 |
| 4〜1 | 「天井及び外板」 については2〜3及び3〜4によること。 |
| 4〜2 | 床下面の金属板等については3〜5によること。 |
| 4〜3 | 「貫通路」については2〜6によるほか、幌を設けていない貫通路には、非常の場合には通行してもよい旨を標示し、かつ、旅客が容易に開くことができる状想で貫通路扉は閉じておくこと。 |
| 4〜4 | 「主回路抵抗器」については2〜9、2〜10及び2〜11によること。 |
| 4〜5 | 「非常措置の標示」については2〜16によること。 |
| 4〜6 | 「消火器」については2〜17〜1及び2〜17〜3によること。ただし、 客室内に設けるものは四塩化炭素のものをさけること。 |
| 屋根 | 品名\項目 | 材料名 | 厚 さ | 燃焼性規格 | 試験番号 | 備 考 |
| 屋根基板 | ||||||
| 屋根絶縁 | ||||||
| 露出金具等屋根上機器名 | ||||||
| 絶縁方法 | ||||||
| 材料名 | ||||||
| 燃焼性規格 | ||||||
| 試験番号 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 外板 天井 内装 | 品名\項目 | 基 板 | 表面塗装等 | ||||
| 材料名 | 厚 さ | 材料名 | 塗装積層の別 | 燃焼性規格 | 試験番号 | ||
| 外 板 | |||||||
| 天 井 | |||||||
| 内 張 | |||||||
| 備 考 | |||||||
| 床 | 品名\項目 | 材料名 | 厚 さ | 燃焼性規格 | 試験番号 | 断面略図 |
| 床 | 1 キーストンプレートの形状等必要寸法記入 | |||||
| 上敷物 | ||||||
| 詰 物 | 2 電線立上り部の略図 | |||||
| 床下面塗装 | ||||||
| 備 考 | ||||||
| 断熱材 防音材 | 部位\項目 | 材料名 | 燃焼性規格 | 試験番号 | 備 考 |
| 天井部 | |||||
| 腰板部 | |||||
| 戸袋部 | |||||
| その他 |
| 座席 日除け 幌 | 品名\項目 | 材料名 | 燃焼性規格 | 試験番号 | 備 考 |
| 表 地 | |||||
| 詰 物 | |||||
| 詰物包 | |||||
| 日除け | |||||
| 幌 |
| 貫通路 | 部位\項目 | 有効寸法 (幅×高さ) | 貫通路の防護 | 扉の形状 | 扉開放保持装置 の有無 | 扉と客室との仕切の有無 |
| 前端 | ||||||
| 中間 | ||||||
| 前端貫通口からの脱出装置 | ||||||
| 主回路 及び電 弧電熱 発生機 器の防 護等 | ヒューズの取付位置 | 閉回路防止装置 | 備考 | |||
| 車両床下断面略図(電線、電線管、密閉ダクト、防熱板、抵抗器等の位置の関係寸法、防熱板の大きさ、リード線の熱的防護方法について記載すること) | ||||||
| 品名\項目 | 防熱版 | 密閉ダクトの防護 | 電線管 | 電線被覆 | ||
| リード線 | 配線電線 | |||||
| 材料名 | ||||||
| 電弧電熱発生機器名 | ||||||
| 機器箱 材料名 | ||||||
| 焦損防止 材料名 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 客室電熱器防護板取付断面略図(防熱版寸法及び取付寸法記入) | ||||||
| 予備灯等 | 予備灯能力 | 停電時使用の可否 | 備考 | ||
| (ワット数×個数) | 自動扉の開 | 放送装置 | 通話装置 | ||
| 非常措置 の標示 |
項目\項目 | 非常停止装置 | 非常通報装置 | 乗客への誘導案内 | 扉開放コック | |||
| 位置 | ||||||||
| 大きさ | ||||||||
| 備考 | ||||||||
| 消火器 | 設置場所 | 1両当たりの個数 | 種類 | 能力単位の数値 | 1個の重量 | |||
| 備考 | ||||||||
|
注
1 記載は本様式によるのを原則とし、構造の相違等により適宜記入欄を変更又は備考欄を利用して記載すること。 2 試験番号とは鉄道車両用材料燃焼性試験成績書番号をいう。 3 昭和44年5月以前に鉄道車両用材料燃焼性試験をうけ、燃焼性規格に適合した材料については試験番号の記載を省略できる。 ただし、この場合、製造者名及び難燃処理法を備考欄に記載すること。 |
||||||||
(別紙2)
| 鉄道車両用材料の燃焼性判定試験依頼等の手続要領 | |
| 鉄道車両用材料の燃焼性の判定は昭和44年5月15日鉄運第81号「電車の火災事故対策に ついて」の記第5項によるものとし、その判定のための試験依頼手続等はこの要領の定めるところによる。 | |
| 1 | 鉄道車両用材料の判定をうけようとするものは、運輸省研究機関受託試験規則(以下試験規則という。)第3条に定める試験研究依頼書1通及び試験片(大きさB5版182mm×257mm)3点を交通安全公害研究所長に提出するものとする。 |
| 2 | 試験依頼書は試験片の品名、商品名、材質、難燃処理法、厚さ等試験実施上必要な事項を記載したものを試験研究依頼書添付するものとする。 |
| 3 | 試験に要する費用は試験規則第9条及び第10条に定めるところによるものとする。 |
| 4 | 燃焼性の判定を行なう材料は次のものとし、試験は原則として単一の材料の状態で行うものとする。 |
| (1)外板、天井・内張、床(表面塗装を含む。) | |
| (2) 床上敷物及び床詰物 | |
| (3) 断熱材及び防音材(ガラス繊維、石綿を除く。)並びに防熱版 | |
| (4) 座席表地、座席詰物及び座席詰物包 | |
| (5) 日除け及び幌 | |
| (6)電線被覆、電線管、絶縁材(特に屋根)及び床下機器箱材料 | |
| (7) その他燃焼性の判定を必要と認める材料 | |
| 5 | 交通安全公害研究所長は別紙様式の試験成績書を試験規則6条に定めるところにより試験依頼者に交付するものとする。 |
| 6 | 交通安全公害研究所長は、試験結果を適宜運転車両課長に通報するものとする。 |
様式1
鉄道車両用材料燃焼試験成績書
試験番号
依頼者名
製造者名
品 名
商品名
難燃処理法
厚 さ
試験実施年月日 昭和 年 月 日
試験成績
判定 |
||||||||||||
(別紙3)