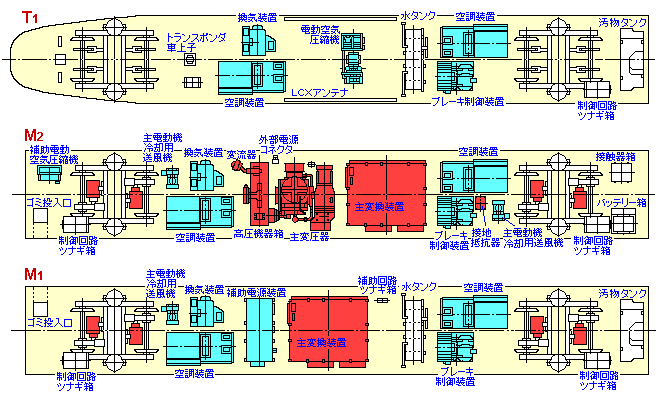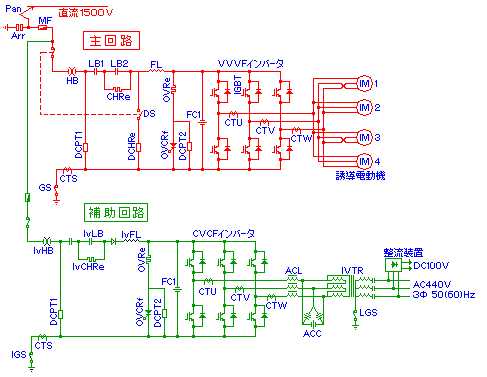
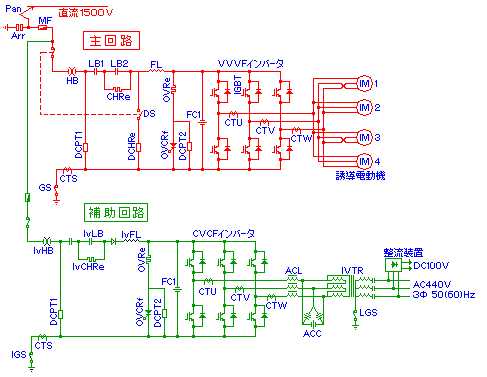 | |
| 記 号 | 意 味 |
| Pan | :パンタグラフ |
| Arr | :アレスタ(避雷器) |
| MF | :主断路器 |
| HB | :高速度遮断機 |
| LB | :単位スイッチ |
| CHRe | :充電抵抗器 |
| FL | :フィルターリアクトル |
| DCPT | :直流電圧検出器 |
| DS | :放電用スイッチ |
| DCHRe | :放電抵抗器 |
| DVCRf | :過電圧抑制サイリスタ |
| OVRe | :過電圧抑制抵抗器 |
| FC | :フィルタコンデンサ |
| CTU、V、W | :電流検出器(U、V、W相) |
| CTS | :電流検出器 |
| GS | :接地スイッチ |
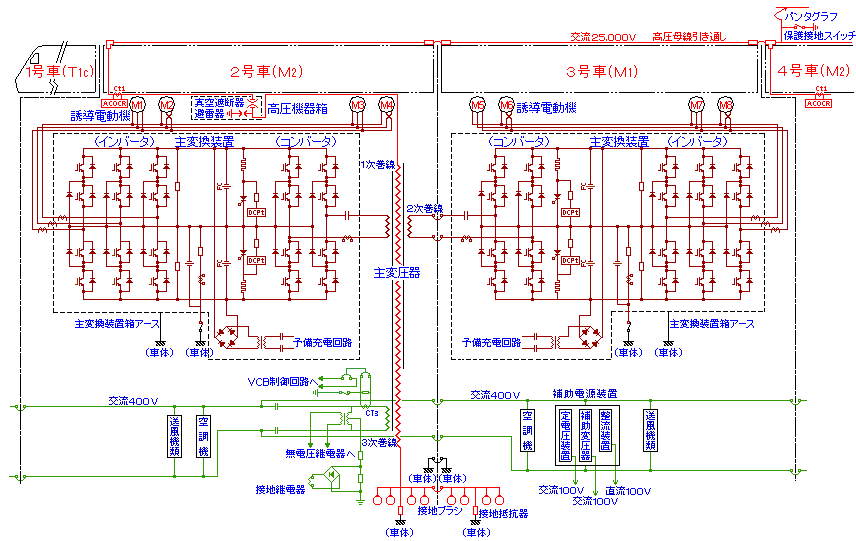
| 機器名 | 略 称 | 機 能 等 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンタグラフ | Pan [Pantograph] |
動力源の電気を走行しながら外部から取り入れる装置をパンタグラフ(集電装置)といい、架線と高速で接触しながら集電し、架線の上下変異に追随し、運転台からの操作で上下できなければなりません。
バネ上昇、空気下降方式が一般的です。架線への押し付け力は5.5kg程度で一定ですが、雪対策として初期押し上げ力を高めにしている例もあります。 形状は、菱形が多かったのですが、部品数の少ない「く」の形をしたシングルアーム式に変わってきています。 | ||||||||||||||||
| 保護接地装置 | EGS [Emergency Grand Switch] |
故障等によって真空遮断器で主回路の遮断ができなくなった場合、電車線に異常が発生して架線を無電圧にしたい場合等に操作して架線を強制接地し、車の安全を守ります。
また、高圧機器箱内の点検時、万一パンタグラフが上昇しても感電事故が起きないように接地しておく役割もあります。 運転台および配電盤のスイッチで電源と空気があれば何時でも投入可能になっていますが、解放する場合は安全上高圧機器箱が完全に閉じている場合のみ可能です。 | ||||||||||||||||
| 高圧機器箱 | 床下に取り付けてあり、真空遮断器、避雷器及び床下用ケーブルヘッドを収納しています。
主要機器を保護しながら点検にも便利であり、かつ人体を感電事故から守るためのものです。 | |||||||||||||||||
| 真空遮断機 | VCB [Vacuum Circuit Breaker] |
主変圧器2次側以降の回路に故障が生じた時に、過電流を0.1秒以下の高速で遮断するもので、通常の場合は主回路の開閉を行う一種の開閉器でもあり、遮断器と開閉器の2つの役目を持っています。
補助空気圧低下、1,3次過電流検知、1,3次接地検知、主変換装置故障等の際に自動的に遮断されます。 | ||||||||||||||||
| 交流避雷器 | Arr [Arrester] |
雷及び開閉サージから機器を保護するためのものです。 | ||||||||||||||||
| 主変圧器 | MTr [Main Transformer] |
特高圧で導入した電力を主変換装置等の各機器に供給するために電圧の変換を行います。
概ね、次のような仕様です。
| ||||||||||||||||
| 主変換装置 | CI [Converter Inverter] (PWM:パルス幅変調) [Pulse Width Modulation] |
主電動機の電源を制御するもので、コンバータ、直流回路フィルタ、インバータ、真空接触器などの主回路機器とゲート論理回路、制御電源などの制御回路機器をまとめた一体箱構造になっています。
コンバータは順変換装置(整流)、インバータは逆変換装置ともいいますが、回生時は同じ機器が逆の役目を果たします。 概ね、次のような仕様です。
|
||||||||||||||||
| 主電動機 | MM [Main Motor] |
平行カルダン歯車形たわみ軸継手方式 強制風冷式 かご形誘導電動機が使われています。
概ね、次のような定格です。
|
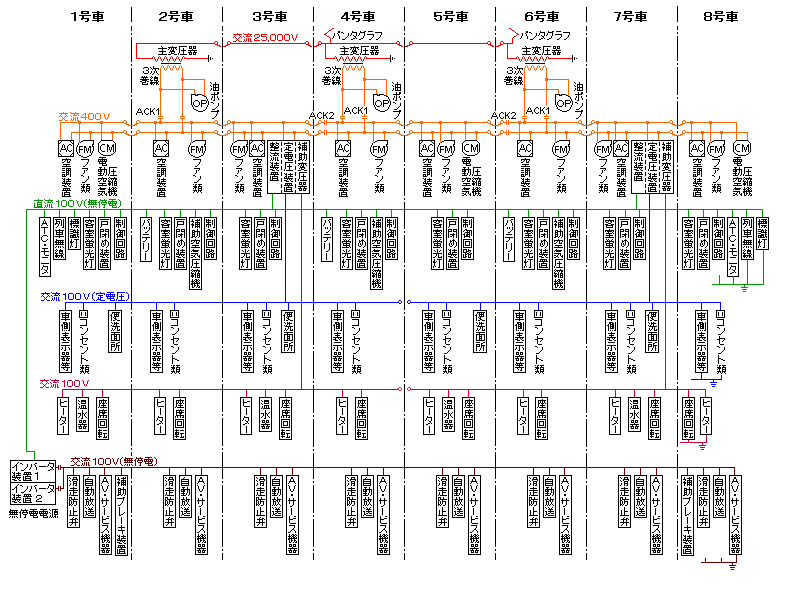
| 電気種別 | 機 器 名 | 機 能 等 |
|---|---|---|
| AC400V | 空気調和装置 | 床下に1両当たり2台搭載されており、圧縮機、室内・室外ファン及びヒータから構成されています。
ファンは定回転数で圧縮機は内蔵のインバータ装置で回転数制御されます。ヒータはON/OFF制御です。 1台当たり 冷房能力:34kW 暖房能力:20kW 循環風量60m3/min です。 |
| 連続換気装置 | トンネル通過中、気圧変動が車内に伝わることも防ぐため、静圧特性の大きい送風機を用いています。
給気30m3/min 排気26m3/min 静圧380mmaq です。給排気量の差は、2両に1個所の便所から排気する分です。 便所排気装置は、排気量8m3/min 静圧380mmaq です。 ドアを開いたときの耳つんを防止するため、車内外を貫通する穴をあけて30km/h以下で車内圧開放弁を動作させ、車内圧を解放しています。 |
|
| 電動空気圧縮機 | 車両の空気源を作るもので、往復形単動2段圧縮 水平対向4シリンダ形です。
空気はブレーキ制御器付属の元空気だめを経てMR管(元空気だめ管)の引き通しに至ります。そこから各空気だめに至りますが、供給空気だめからは台車の空気ブレーキへ、制御空気だめからは制御空気回路へ供給されます。 MR管が、8kg/cm2でONし、9kg/cm2でOFFします。 |
|
| 補助電源装置 | 静止形変換装置ともいい、車両搭載の各機器に電源を供給するための電源になるもので、定電圧(CVCF)変圧器、補助変圧器(ATr)、整流装置等から構成されます。 | |
| DC100V | 戸及び押さえ装置 | ドアの開閉と、ドアを車体に押し付けて気密を確保します。 |
| 車内照明 (一部予備灯を兼用) |
インバータ点灯方式で、セクション通過時の瞬停によるツラツキを防止するために直流電源としています。 | |
| 補助空気圧縮機 | 出区時など圧力空気のないときに、パンタ上昇やVCB投入用の圧力空気を作ります。 | |
| 標識灯 | 先頭 150W/50W×シールドビーム4灯 後部4W×LED2灯です。 |
大きく分けて、次の2つに分けられます。
○主変圧器3次回路系統
主変圧器の3次側出力線で、そのまま直接主変圧器の油圧ポンプモータの電源となる系統(延長給電なし)と交流接触器(ACK1)経由で、ユニット単位(T車を含む全8両編成なので、3両、2両、3両単位)で空気調和装置、補助電源装置、
電動空気圧縮機、換気装置や主回路機器のブロアの電源となる系統があります。(ACK1切り、ACK2入りによる延長給電あり)
○補助電源装置を電源とする系統
補助電源装置APU(Auxiliary Power Unit)は、各低圧用機器用の電源をまとめたもので、静止形変換装置とも呼ばれています。
図の例では各ユニットに1台ずつ搭載されており、通常は3台並列同期をしていますが、1台故障した場合でも正常運転できるように、つまり2台で編成全体に供給するのに必要な負荷容量を持っています。
主に、次のような機能を持つ機器を一体構造にしています。
| 整流装置 | 交流400Vを直流100Vに変換するもので、この電源自体は瞬停がありますが、バッテリに供給しているため、瞬停時等には逆にバッテリから電気が送られるので、無停電電源になります。
停電があっても動作する必要がある制御回路の電源や瞬停時のちらつきのないよう蛍光灯の電源等になります。 |
| 補助変圧器 | 交流400Vを交流100Vに変換するもので、架線の電圧変動、瞬停等の影響をそのまま受けるので、ヒーター等あまり品質の要求されない機器の電源になります。 |
| 定電圧装置 | 同じく、交流400Vを交流100Vに変換するものですが、出力電圧の変動範囲を一定以下に押さえて品質を確保したもので、表示灯やコンセントなどの電源になります。 |