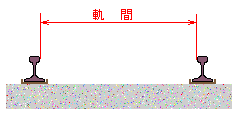|
| ||||||||||||||||||||||
2.軌間の異なる区間の直通運転方法
旧国鉄時代に東北新幹線が盛岡まで開業した際、東京(上野)-札幌の新幹線・在来線直通運転を検討し、台車はきかえ方式、 軌間変換台車方式の両面で検討されましたが、前者は変換基地等の工事費・要員、交換時間、冬季の台車凍結等の問題から、 後者は当時の電車の電動機はまだ直流機であり大出力の直流電動機を狭軌の台車に変換機構を含めて搭載するのは困難等の 理由から実用化されませんでした。国内、外では現在どの様な直通運転方式が検討、実用化されているのでしょうか。
○レールを3本または4本引く
複数のゲージに合わせて線路を引くもので、3線あるいは4線が考えられます。3線の場合は一方の線路を共通で使うもので、 この方式で複数の軌間の路線を直通運転しているのは小田急電鉄(1.067m)と箱根登山鉄道(1.435m)が3線軌で 小田原-箱根湯本を行っており、山形、秋田新幹線は在来線(1.067m)を標準軌に改軌し、普通電車も標準軌の車両を 新製して投入しましたが一部JR貨物の貨物列車が走行する区間は3線にしています。4線は架線の位置が中央で都合がいい のですが、レールが1本増える、分岐器構成の難しさ等から国内営業線で採用されている例は無いようです。
○台車を交換する
いわゆる台車はきかえ方式で、国内の営業線では実績がありません。特殊な例では、近鉄の橿原神宮前駅にある4線の 台車振り替え場で狭軌である南大阪線の車体を広軌区間にある五位堂検修基地に回送するために使っています。 台車も貨車に積んで同時に回送するそうです。
海外では、貨物列車の直通運転のためにロシアとポーランド、スペインとフランスの国境間で行われているといいます。 貨車の車体をジャッキで持ち上げ、その間に別のゲージの台車と交換するもので、ジャッキ等の設備と作業者が必要になり 時間もかかります。電車の場合は更に車体・台車間の電気配線等の縁切り作業があり、困難性が高くなります。
○車両側で軌間を変更する
現在開発が進められている方式で、車両で対応するので地上設備としては軌間変換設備のみで済みますが、軌間変換電車を 新たに開発する必要があります。車両の走行安全性を支える台車の車軸・車輪などの駆動部分に可動部をどう構成するかがポイントです。 電車で実用化された例はなく、走行試験を十分行って走行安全性、各部の強度、軌間変換の確実性等の確認が不可欠です。
海外では、スペイン国鉄の軌間変換式タルゴ列車が有名で、後に詳しく述べます。
○改軌する
直通運転するために軌間を変更してしまうもので、山形新幹線(福島-新庄間)、秋田新幹線(盛岡-秋田間)は1.067m から1.435mに変更しました。改軌するためには工事費、工事期間の代行輸送、建築・車両限界等の問題が有りますが、 軌間を広げる際に、併せて枕木や道床を交換する事による線路強化や局部の線形変更等が可能で、高速化が可能になる面もあります。
千葉県の新京成電鉄は昭和34年8月に1.067mから1.435mに改軌したようですが、近鉄でも過去に改軌した線があるそうです。
3.スペインのタルゴの方式はどんなもの?
○タルゴ列車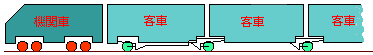
客車列車で軌間変換を行っていることで有名なタルゴ列車は1969年スペインのバルセロナ~スイスのジュネーブ線で 営業が開始され、1981年6月からはマドリッド~パリ間に自然振り子式寝台特急が登場し、最高速度160km/hで運転されています。 この列車は、機関車けん引の特急旅客列車で、アルミ製13.14m長車体の客車は1軸の連接台車方式となっていて、スペイン(1.668m)、 フランス(1.435m)間を直通運転する際、国境駅の軌間変換区間で機関車を交換し、客車の連接台車のみ軌間変換設備で自動変更しています。
編成のイメージは右図のとおりで、客車は1軸の連接台車になっており、また舵取りリンクによってカーブで台車(輪軸)が ラジアル方向を向くようにして舵取り機能を持たせています。
| 連接部断面と輪軸部の形状 |
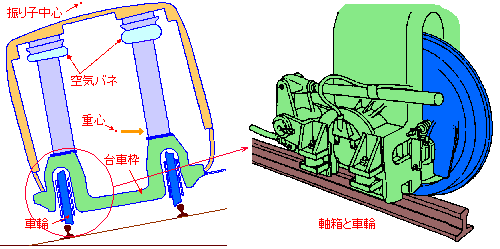 |
連接部の断面は右図の左のとおりで、空気バネを車体間の上部に設けることによって曲線走行時に「自然振り子」的な 作用を持たせることができ、乗り心地の向上等に寄与している点も特徴的です。連接の1軸台車なので台車構造も右図の右のようなシンプルなものです。
○タルゴの軌間変換機構
タルゴのもっとも特徴的な軌間変換メカニズムを見てみましょう。
| タルゴの軌間変換地上設備 |
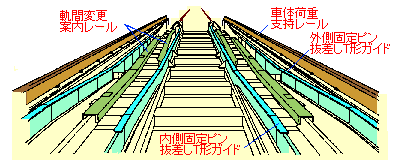 |
タルゴの軌間変換地上設備を正面から見ると右図のようになっています。一番外側に車輪に変わって車両の重量を支える車体荷重支持レールがあり、その間に車軸の左右方向の動きを固定しているカンヌキ状の固定ピン解放、挿入用のT形ガイドレール、レールを挟んで軌間を変更する軌間変更案内レールがあります。
客車が機関車に押されて図の上方(軌間 1,668mm)から下方に向かって走行するときの軌間変換の順序は、 下の図のようになっています。
| 軌間変換の様子 | 変換過程の説明 |
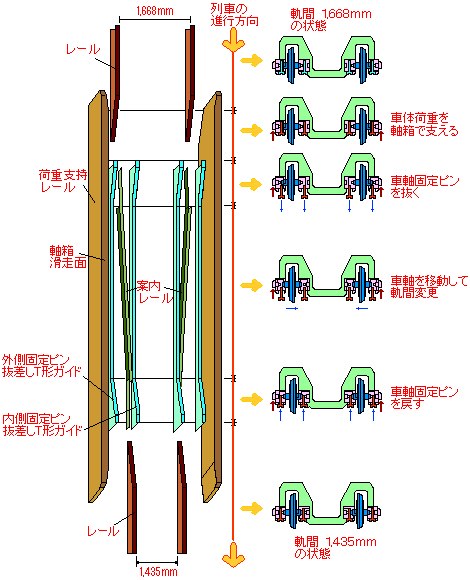 |
|
4.日本で今試験している軌間変換電車はどのようなもの?
(1) 発端は平成6年6月の運輸技術審議会答申(「21世紀に向けての鉄道技術開発のあり方について」)の重点技術開発課題 (SUCCESS21計画)のテーマの1つとして乗り継ぎ抵抗の解消等のために軌間可変台車の開発が取り上げられました。
これを受け、運輸省、日本鉄道建設公団、(財)鉄道総合技術研究所が開発を始めました。
(2) どんな車両、台車を開発しているのか?
今回試作された軌間可変電車の主な仕様は下表のようになっています。主な特徴としては、
- 在来線に入ることから、在来特急並の車体の大きさです。秋田新幹線の「こまち」とほぼ同じサイズです。
- 最高速度は新幹線区間300km/h、在来線区間130km/hで、5電源対応です。
- 台車は車輪とモーターを一体化したDDM(ダイレクト・ドライブ・モーター)駆動方式(A方式台車)と、従来の台車と同様な 平行カルダン駆動方式(B方式台車)の2種類です。
| 編成 | |||
|---|---|---|---|
| 形式 | MC1 | M1 | MC2 |
| 車両総重量 | 48t | 42t | 48t |
| 車両限界 | 普通鉄道(非縮小) | ||
| 電気方式 | 交流25/20kV 50/60Hz、直流1.5kVの5電源 | ||
| 最高速度 | 新幹線300km/h 在来線130km/h | ||
| 車体構造 | アルミニウム合金 機密構造 | ||
| 車両長 | 23.075m | 20.5m | 23.075m |
| 車体幅 | 2,945mm | ||
| 車体高さ | 3,650mm | ||
| 台車形式 | RTX9A、9B、9C(予備) | RTX11 | RTX10A、10B |
| 台車方式 | 操舵機能付きボルスタレス | ボルスタレス | 操舵機能付きボルスタ付き |
| 駆動方式 | 同期電動機・DDM駆動 | 誘導電動機・平行カルダン駆動 | 同期電動機・DDM駆動 |
| 軸距 | 2,200mm | 2,500mm | 2,200mm |
| 制御方式 | 3レベルIGBT VVVFインバータ駆動、回生ブレーキ併用電気指令空気ブレーキ | ||
| MM出力 | 95kW×8個=760kW | 200kW×4個=800kW | 95kW×8個=760kW |
5. 軌間変換台車の特徴、構造は
軌間可変電車の最も大きな特徴はその台車にあります。今回試作された台車は2種類有り、 国内の通勤電車、新幹線では初めて採用された電動機・車輪一体駆動方式と実績のある平行カルダン駆動方式の2つです。2つの方式の特徴を簡単に整理したのが下の表です。
| 比較項目 | 電動機・車輪一体駆動方式(A方式) | 平行カルダン駆動方式(B方式) |
|---|---|---|
| 駆動方式 | 車輪一体形主電動機を採用し、車輪を直接駆動する | 台車装架の主電動機を採用し、継手、歯車装置を介して輪軸を駆動する |
| 車軸と車輪の回転 | 走行中、1軸の左右の車輪は構造上独立に回転できる | 走行中、1軸の左右の車輪は車軸を介して一体で回転する |
| 軌間の変換 | 固定車軸上を「車輪+電動機」一体でスライドさせる | 車輪を圧入した外筒を回転する車軸上のコロスプラインを介してスライドさせる |
| 得失 | 独立車輪方式なので高速でも蛇行動は発生しないが、片方に偏奇したまま走行する可能性があり、操舵機能が必要になる場合がある。 | 実績のある平行カルダン駆動方式であり、車輪車軸が一体なので自己操舵機能が期待できるが、コロスプラインの信頼性確認が必要。 |
6. 軌間変換台車の構造
2種類の試作台車の形式は、A方式のものが更にRTX9(ボルスタレス)、RTX10(ボルスタあり)の2タイプがあり、B方式のものはRTX11という名前が付いています。その構造は下図のようになっています。RTX9とRTX10の違いは枕ばりの有無の差で変換機構は同一なのでRTX9台車を示しました。
| RTX9(同期電動機・DDM駆動) | RTX11(誘導電動機・平行カルダン駆動 |
| ボルスタレス。操舵機構付き | ボルスタレス。操舵機構なし |
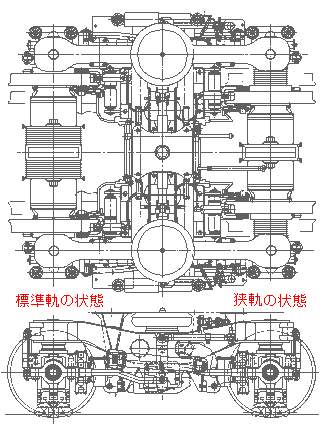 | 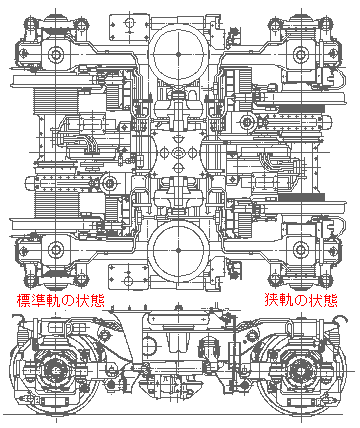 |
7. 軌間変換部の機構と軌間変換過程
これらの台車で最も特徴的な軌間変換の部分を見てみます。(1) A方式台車の場合
(ア)輪軸の構造
| RTX9輪軸断面 |
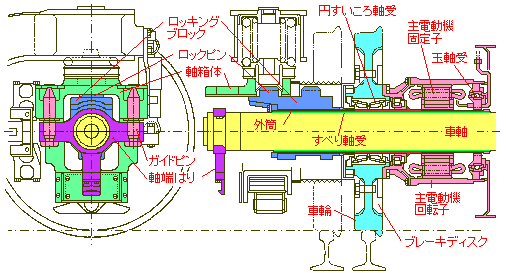 |
回転するのは外筒にベアリングを介して取り付けられている電動機とそれと一体になった車輪のみで、外筒、ロッキングブロック、 車軸は回転しません。この車軸が回転しないというところが特徴的です。
(イ)軌間変換過程
軌間変換の過程は下図の通りです。
変換中の列車速度は概ね5~15km/hが予定されており、変換中の電動台車は空転しないよう主回路が切られます。従って走行するためには他の電動車両が必要で1両編成では不可能です。
| 変換軌道 | 変換過程 | 説明 |
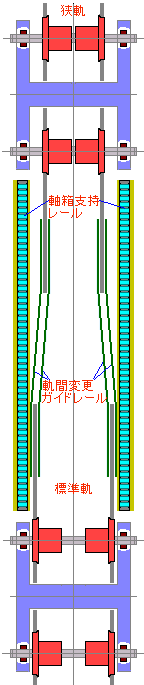 | 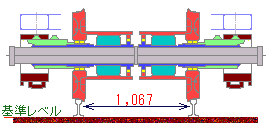 | 狭軌走行状態 車体荷重は軸箱-車輪-レールと伝わる。 |
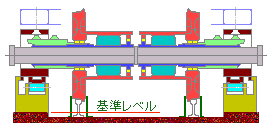 | レールを徐々に下げる。同時に車体も下がろうとするが、軸箱下に軸箱支持レールがあるので車体は下がらず、輪軸だけが下がり、ロッキングブロックのロックピンが軸箱から外れて左右に動けるようになる。 車体荷重は軸箱下の軸箱支持レールで支える。車体の上下動はない。 | |
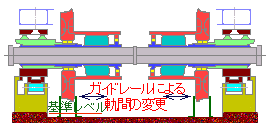 | 案内レールによって軌間が変更される。 | |
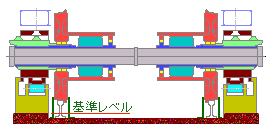 | 所定の位置まで軌間を変更する。 その後レールが徐々にあがり、それにつれて輪軸も上がりロッキングブロックのロックピンが軸箱にはまり固定される。 | |
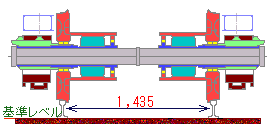 | 標準軌走行状態 |
(2) B方式台車の場合
平行カルダン駆動方式台車の輪軸断面は右図のようになっています。車軸の外側にある円筒形の筒(外スリーブ)に 車輪、軸箱が取り付けられてあり、これらが一体となって軌間にあわせて左右に移動します。外スリーブの軸端側と車軸端に はめられた内スリーブ間にはコロ式スプラインがあり、回転トルクを伝えると同時に、軌間変換中はここで左右にスライドします。 車軸と外筒の間に滑り軸受けが入っているので移動できるわけです。
つまり、誘導電動機のトルクは減速歯車装置を介して直接車軸に伝わり、内スリーブ-コロスプライン-外スリーブ-車輪と 遠回りして伝わります。
左右の車輪と車軸は一体で回転しますので、従来の平行カルダン台車と同じ特性を示し、いわゆる「自己操舵機能」を持っています。
図では分かりませんが、左右方向の固定は軸箱と軸箱はり間で行い、それぞれに相対するように設けられた縦溝にロック用のスライドストッパを挿入して行います。 施錠用バネによって常時下方に押しつけられたスライドストッパを軌間変換区間で錠コロ転動面を上げることによってカム機構を通じて強制的に押し上げるとストッパの位置によってロックが外れて左右に動けるようになるのでその間に軌間変換案内レールによって軌間を変換します。変換後は錠コロ転動面を下げることにより ストッパがバネで下がり左右方向の動きがロックされます。
| RTX11輪軸断面 |
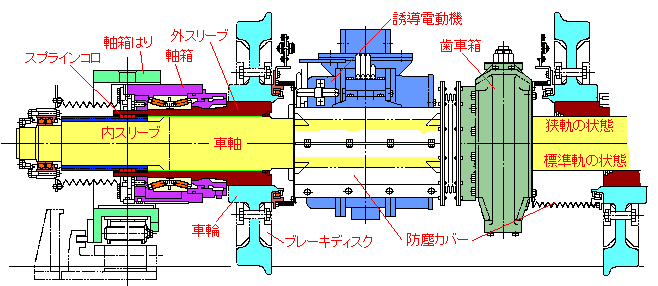 |
8. 軌間変換するための地上設備
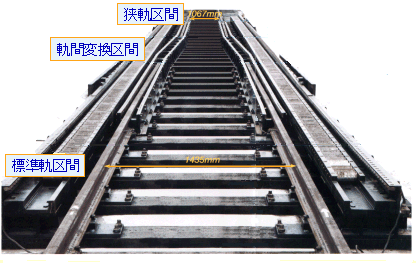 実際のA台車用軌間変換設備のイメージは右の図のようになっています。少し見にくいですが軌間変換区間のレールが少し下がっていること、
変換区間の中央部にはレールがなく軌間変換が行われること、一番外側に軸箱支持レール(実際は円筒コロを沢山並べている)がある等が
分かります。
実際のA台車用軌間変換設備のイメージは右の図のようになっています。少し見にくいですが軌間変換区間のレールが少し下がっていること、
変換区間の中央部にはレールがなく軌間変換が行われること、一番外側に軸箱支持レール(実際は円筒コロを沢山並べている)がある等が
分かります。この写真は試作レベルのもので、また、A方式、B方式のという変換方式によって構造の違いがありますが、車体荷重を軸箱支持レールで支え、自由になった車軸軸箱のロック装置をはずして軌間を変更し、変換が終了したら車体荷重を軸箱支持レールから車輪に戻すという基本的な考えは共通です。
9. 開発行程
開発は下の表にあるように平成6~8年度の第1ステップと平成9~12年度の第2ステップの2つの段階で行われており、 今は第2ステップの最終年度に当たります。それぞれ、表中にあるような事柄について開発が進められていました。
| 開発行程 | 第1ステップ | 第2ステップ | |||||
| 年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 |
| 試験行程 | 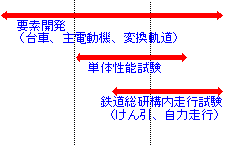 | 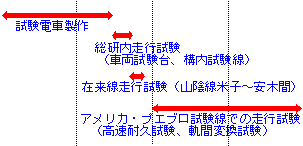 | |||||
| 主なテーマ | 要素技術開発 | 試験車両による走行試験。実用化検証 | |||||
10. GCT01形式軌間変換電車の走行試験経過と成果
開発期間中、現車走行試験を実施していますが、それぞれの走行試験時の編成、行程と主な成果は下の図表のとおりです。(1) 国内走行試験Ⅰ(平成11年1月22日~30日、山陰線米子-安木間)
・JR西日本の山陰線米子-安木間8.8km下り線で(上りは回送)夜間線路閉鎖をして行った。
・3両編成だが、中間車は既存の在来台車を使いT車としたため、2m1T編成となっている。
・最高速度100km/hまで速度向上し、安定した走行だった。
| 米子走行試験 (←進行方向) |
呼称 | MC1 | T | MC2 | |||
| 編成 |
|
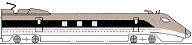 |
|||||
| 台車 | RTX9A | RTX9B | RTR235 | RTR235 | RTX10B | RTX10A | |
| 記 事 |
・下り進行方向第1軸がPQ軸(計2本) ・21日後藤総合車両所構内走行、22日に35km/hから5km/hずつ速度向上、1日3往復。28日最高速度100km/h達成。 ・操舵台車の操舵あり | ||||||
(2) プエブロ走行試験Ⅰ(平成11年4月12日~平成12年4月19日、アメリカのプエブロ試験線)
・A方式台車の2両編成による耐久試験を行い、走行距離30万kmを達成した。
・この間の最高速度は243km/hだった。
| 2両編成 (1999.4.12~2000.4.19) |
呼称 | MC1 | MC2 | ||
| 編成 | 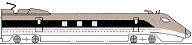 |
||||
| 台車 | RTX9A | RTX9B | RTX10B | RTX10A | |
| 記 事 |
・1999.4.12~2000.4.19間、2両編成による速度向上、耐久試験 | ||||
(3) プエブロ走行試験Ⅱ(平成12年5月20日~)
・A方式台車の2両にB方式の中間車を加え、3両編成による耐久試験を行う。
・A方式台車60万km、B方式台車30万kmの耐久試験を平成12年度に行う。
| 3両編成 (2000.5.19~2001.3?) |
呼称 | MC1 | M1 | MC2 | |||
| 編成 | 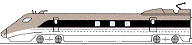 |
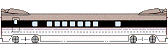 |
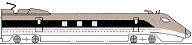 |
||||
| 台車 | RTX9A | RTX9B | RTX11 | RTX11 | RTX10B | RTX10A | |
| 記 事 | ・2000.5.20~6.2間速度向上試験。 | ||||||
11. プエブロ試験線について
プエブロ試験線は、アメリカのコロラド州にあるTTCI(Transportation Technology Center inc.) 所有の試験線で、沢山の線がありますが、下の図の赤線で示した外周のRTT線は全長21.7kmで、交流25,000V、標準軌(1,435mm)です。プエブロ試験線はアメリカ運輸省に所属していた時期もあったそうですが、現在は民営化されて、全米輸送協会の子会社になるTTCIの所有になっています。
管理棟の左に見える緑色に着色した線はJR線で、軌間可変電車専用の検修庫であるJRF(Joint Research Facility)を含めて軌間可変台車試験専用に建設されたものです。
JRFの中にはリフティングジャッキと簡単な検修設備の外に、軌間変換設備を設けて図の上部の唯一の狭軌区間と変換耐久試験等を行います。
台車抜き等はTTCIの設備である検修建家(CSB)で行っています。
日常の点検やデータ収集、運転操作は研修を行った上でTTCIの職員が行っています。
| プエブロ試験線 | 主な諸元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
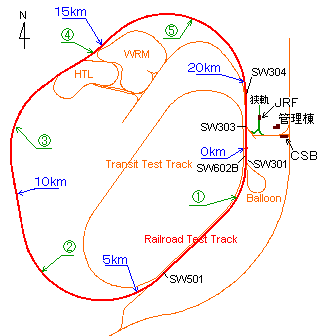 |
○主なプロフィール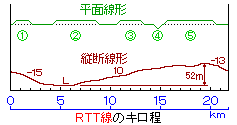 ○曲線諸元
その後、残りも全て交換した。 |
| 試験走行中のGCT01 |
 |
| 運転台から前方を見る |
 |
| JRF |
 |