7. 振り子車両はなぜ必要? 原理は? どんな種類があるの?
1. 曲線通過と列車速度
列車が曲線を走行するときには曲線外側への遠心力が働き、そのままだと乗り心地の悪化、外側への転倒の危険性、外側線路の輪重、
横圧増による軌道保守量の増等の問題がおきます。従って、一般にこの遠心力を打ち消すために内外軌道に高低差を設けて軌道に傾斜を付けますが、
この傾きをカントといっています。
半径Rの曲線を速度Vで走行したときの遠心加速度とバランスするようにカントCを付けたとすると、軌間G、重力加速度Gの場合、
α=V2/GR=C/G
の関係式が成り立ちます。たとえば在来線で半径800mの曲線を120km/hで走る場合に超過遠心力を感じない必要カントを計算すると、151mmになります。
大きなカントを設ければいくらでも曲線での速度を上げられそうですが、曲線の外側からの風によって内側に転覆しないという安全面と曲線上に停まった場合に車体の傾斜で乗客があまり不快感を感じないようにという乗り心地の面から在来線で105mm、新幹線で200mmという最大のカント量(Cm)が決められています。
先程の例だと151mm−105mmの46mmカント量が不足するため、46/1067=0.043Gの遠心力を感じてしまいます。このカント不足量(Cd)も外側への
転覆に対する安全性、乗り心地等の面から、在来線で60mm(一般のEC、DC)、70mm(非振り子の特急)、110mm(振り子特急車)、新幹線で90mm以下としています。
カントは寸法で表しますが、狭軌と標準軌では分母となる軌間が異なるため注意が必要です。
振り子特急車の場合、図のように超過遠心力が振り子作用によってキャンセルされ乗り心地が改善されるため、試験の結果から110mmという大きなカント不足量を採用できる、つまりより高速で曲線を通過することができるわけです。
直線(カント0)からいきなり曲線(たとえば80mmのカント)に入る訳にはいきませんから、直線と曲線の接続箇所にはカントを連続的に増減させる緩和曲線という曲線を挿入します。その長さは列車の速度、カントに応じて決められます。JRの在来線などが整備されたSLの時代は最高速度が低かったため曲線半径もカントも一般に小さいため、曲線速度向上のためカントを上げようとしても緩和曲線長が不足し上げられず、速度向上が難しいのですが、振り子を採用することによって大きなカント不足が認められるので効果があるわけです。
一旦緩和曲線が敷設されるとその後延伸することは線形を変えない限り困難となるので新設、改良時には将来の最高速度を予測して必要十分な長さの緩和曲線長を設定しておく必要があります。
次の表は、曲線毎の車両種別別最高速度の例で、振り子の曲線高速走行の優れているのがわかります。
| 曲線半径(m) | 一般 | 高性能列車 | 381系自然振子 | 制御付き振子の例 |
|---|
| 200 | 50km/h | 50km/h | 65km/h | 70km/h |
| 250 | 55 〃 | 60 〃 | 75 〃 | 80 〃 |
| 300 | 60 〃 | 65 〃 | 80 〃 | 85 〃 |
| 350 | 65 〃 | 70 〃 | 85 〃 | 90 〃 |
| 400 | 70 〃 | 75 〃 | 95 〃 | 100 〃 |
| 450 | 75 〃 | 80 〃 | 100 〃 | 105 〃 |
| 500 | 80 〃 | 85 〃 | 105 〃 | 110 〃 |
| 600 | 85 〃 | 90 〃 | 110 〃 | 120 〃 |
| 700 | 90 〃 | 95 〃 | 115 〃 | 125 〃 |
| 800 | 95 〃 | 100 〃 | 120 〃 | 130 〃 |
| 1000 | − | 105 〃 | | |
| 1200 | − | 110 〃 | | |
| 1400 | − | 115 〃 | | |
| 1600 | − | 120 〃 | | |
2. 振り子車両とは
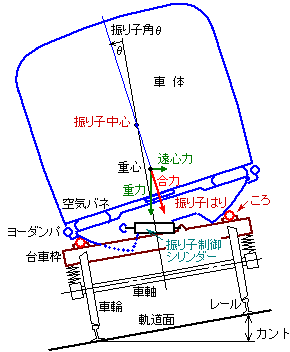 振り子車両は曲線を通過するとき車体を図のように内側に傾かせ、乗客が感じる超過遠心力を打ち消すもので、大きく分けて遠心力の作用で自然に傾斜させる日本に多い自然振り子方式と加速度計を付けておきそれを打ち消すように油圧等で強制的に傾斜させる海外に多い強制振り子方式があります。
振り子車両は曲線を通過するとき車体を図のように内側に傾かせ、乗客が感じる超過遠心力を打ち消すもので、大きく分けて遠心力の作用で自然に傾斜させる日本に多い自然振り子方式と加速度計を付けておきそれを打ち消すように油圧等で強制的に傾斜させる海外に多い強制振り子方式があります。
自然振り子は遠心力を利用するので原理は簡単で信頼性が高いのですが、強制式はジャイロや加速度計を設けて油圧等で制御するので複雑で信頼性が低くなりやすい面があります。強制式の場合、高速で曲線走行中に振り子がフェールすると次のカーブが反対向きだと逆向きの大きな超過遠心力を受け、乗客は飛ばされることになりかねないなどの危険性があり、高い信頼性と異常時対応を考慮しておく必要があります。
日本で最初に営業線に使われた振り子車両は、昭和48年(1973)7月10日の中央西線・篠ノ井線電化開業に合わせて名古屋ー長野間に登場した381系特急電車です。最高速度は120km/h、曲線通過速度は+20m/hで、軽量・低重心化を図るため、アルミ車体とし、通常屋根上にある空調等の機器を床下に持って行きました。屋根上にはパンタグラフと通風器以外の機器がないすっきりした外観ですぐ振り子車とわかりましたが、最近の制御付き振り子は空調を屋根上に搭載しているものも多く、外観からだけでは判りにくくなったようです。
日本で最初に車体傾斜の試験を行ったのは昭和36〜7年頃で、SE車を使って小田急と三菱電機が強制振り子方式の試験を行っていますが、実用化はされませんでした。
381系を実用化した国鉄は、振り子や連接による操舵機構等の試験のために3車体連接構造の591形在来線用試験電車を昭和45年3月に製作し、信越本線などで試験を繰り返しました。その結果、曲線通過中の乗り心地改善が見込めたためころ式自然振り子を381系に採用することになりました。
3. 制御付き振り子車両の誕生まで
中央線での曲線通過速度を大きく向上した381系特急電車ですが、特に立っている乗客や乗務員から乗り物酔い等乗り心地の苦情があり、改善が望まれていました。この原因はころ部等に摩擦抵抗があるため、たとえば曲線入口では遠心力が摩擦力に打ち勝ったときに突然大きく動き出すためで、緩和曲線が短いこともありスムーズな動きにはなっていませんでした。
そこで登場したのが制御付き振り子車両です。強制振り子にしても遠心力を検知して動作させるため遅れが生ずるのが避けられないため、実績のある自然振り子に摩擦抵抗をキャンセルするような力を付加すれば問題は解決するというわけです。
そのためには線路線形を正確に車両に覚え込ませると同時に車両自身が自分の位置を常に把握しておく必要がありますが、昭和55〜6年頃設計が進められた東北・上越新幹線200系電車にはモニター装置が搭載され、自車の位置を常に把握して自動放送装置等により各種の情報サービスを計画するなど、マイコン等の情報処理技術の進歩、コストダウンにより技術的には実用化できる状況になってきました。
昭和57年頃から国鉄は高速道路との競争等を意識し高性能特急電車の開発を進め、ボルスタレス台車や制御付き振り子台車の基礎技術開発、実用化試験が行われ、ボルスタレス台車は通勤電車の205系以降の車両に採用されました。昭和62年4月に国鉄は分割民営化されましたが、振り子はJR移行後も開発が進められ、平成元年3月11日のダイヤ改正から登場したJR四国のTSE2000系特急気動車で世界で初めての制御付き振り子が実用化されました。この車両は制御付き振り子以外に25‰の登り勾配を95km/h以上の速度で走行できる性能を持ち、それまでの気動車のイメージを一新した意欲的な車両でした。
4. 制御付き振り子の制御の仕方
車両には走行線区の線形データ、即ち曲線の位置、半径、緩和曲線の長さ、カント量等を事前に記憶させておきます。これは最初手入力で大変でしたが、最近は走行させながら自動的に軌道データを収集、作成するシステムが採用されています。
通常、両先頭車にCC装置(Comand Controller)と地点検知用車上子を設けており、始発駅を基準に車輪の回転数から計算した自車の位置情報とその地点の線路情報から必要な振子シリンダー制御指令を編成全体に出します。車輪径の変化や空転等による検知位置のずれは、あらかじめ記憶して判っているATS地上子の位置で補正を行います。
各車両にはこの指令を受けて車体傾斜の振り子制御シリンダーの制御を行うTC装置(Tilt Controller)を設けており、編成内の位置に応じて振子制御のタイミングを調整しています。
曲線データに応じてどのような大きさの制御指令をいつ、どう出すと一番乗り心地がよいかは車両速度、線形等によって異なるため色々な試験の結果決められました。緩和曲線にはいる少し前から制御を始めています。振子作用は速度50km/h以上、曲線半径200m以上とし、低速時や急曲線では振子作用を行わないようにしています。
振り子の基本は車両への遠心力であるため、制御異常があっても制御シリンダーのカでは車体を逆に振らせるだけの力は無く安全な機構となっています。制御シリンダーで制御するので強制振り子ではないかといわれる場合があるようですが、この辺が「自然振り子」と呼ぶ理由でしょうか。
5. 日本での強制振り子
制御付き振り子機構は構造が複雑でシステムが高価ということから空気バネを利用した車体傾斜システムをJR北海道が201系通勤気動車で実用化しました。車両に取り付けたジャイロで曲線を検知し、車体左右定常加速度を抽出して外軌側空気ばねに圧力空気を供給し、車体を最大2度傾斜させ、
遠心力を緩和するものです。外側の空気バネは車体に働く遠心力で圧縮されますのでそれも補って2度傾斜させるわけです。システムの信頼性の向上、空気ばねの応答性向上等によって可能になりました。曲線情報は先頭車で検知、情報は引通し線で後続車両に伝えるため、2両目以降は遅れを補償できますが、
先頭車は制御付き振子車両と異なり、曲線を検知してから傾斜を開始するため、遅れが生じるのは避けられず、それをいかに小さくするかがポイントです。
6. 振り子関連技術
(1) 車体傾斜方式の種類
振り子車両の基本構造は、台車と車体間の車体側に「振り子はり」を設け,これを振り子中心に対して円弧運動させることで車体を傾けます。振り子はりの支え方により、「ころ式」「曲線ガイド式」「リンク式」という種類があり、線区条件等を考慮して方式が選ばれています。
・ころ式
381系に採用されて以来最も一般的な方式で、台車枠の上に左右一対の直径20cmくらいの鉄製ころを置き、この上に曲面状の受け台の付いた振子はりを載せるものです。埃の進入を防ぐ必要がありますが、構造は簡単です。
・ベアリングガイド式
小さなボールベアリングを曲線状に配置し、この間をガイドレールが動く構造で、抵抗が小さく、ゴミや雪の進入に強いため、耐寒耐雪構造の求められるJR北海道で最初に採用されましたが、JR西日本の283系などにも使われています。
・リンク式
リンク式は台車枠と振子はりをハ形に2本のリンクで結び、油圧シリンダで台車砕と振子はりを左右にずらして振子はりを傾けるもので、イタリアなどの海外の強制振り子車両によく使われています。
(2) パンクグラフの位置調整方法
パンタグラフは車体の屋根上についているので振り子で車体が傾くとそれに応じて架線中心から外れる方向に動くため、架線の位置調整、車体傾斜角や振り子中心高さの制限等が必要でしたが、車体が傾いてもパンタグラフの位置は変わらないようにすることによりこれらの問題を解決しました。
・ワイヤ式
JR四国の電車特急8000系で採用した方式で、屋根上に円弧状のガイドレールを置き、この上にパンタグラフを載せて台車間とワイヤで結んでおき、車体が傾斜したときには台車との関係が直線時と同じ状態を保つようにパンタグラフがワイヤに引かれて屋根上のレールの上を移動するようにした方式です。パンタグラフ直下の台車を見ると、台車枠から2本(1本は予備)のワイヤが車体内を通って屋根上に伸びているのでわかります。
台車とパンタグラフの間隔は車体・台車間の空気ばねの上下変位に応じて変わりますが、左右のワイヤの伸び縮みが等しいときにはパンタグラフ側のローラで巻き取って調整します。
・台車枠直結式
JR東日本のE351系やJR九州の883系で採用した方式で、車体に床下と屋根を結ぶ穴を設け、台車枠から直接屋根上までT形をしたパンタグラフの支持枠を延ばした方式です。車体の傾き、上下の動きとは完全に緑が切れますが、支持枠が前後方向に動いてしまうと困るので屋根上のリンク機構で抑えています。
この方式は客室スペースが犠牲になりますが、ワイヤ式のようなワイヤメンテナンスは不要です。
索引に戻る
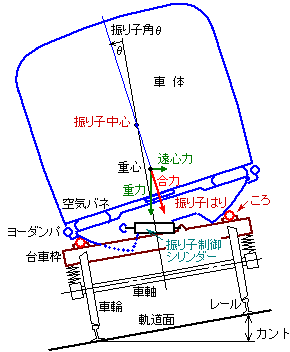 振り子車両は曲線を通過するとき車体を図のように内側に傾かせ、乗客が感じる超過遠心力を打ち消すもので、大きく分けて遠心力の作用で自然に傾斜させる日本に多い自然振り子方式と加速度計を付けておきそれを打ち消すように油圧等で強制的に傾斜させる海外に多い強制振り子方式があります。
振り子車両は曲線を通過するとき車体を図のように内側に傾かせ、乗客が感じる超過遠心力を打ち消すもので、大きく分けて遠心力の作用で自然に傾斜させる日本に多い自然振り子方式と加速度計を付けておきそれを打ち消すように油圧等で強制的に傾斜させる海外に多い強制振り子方式があります。