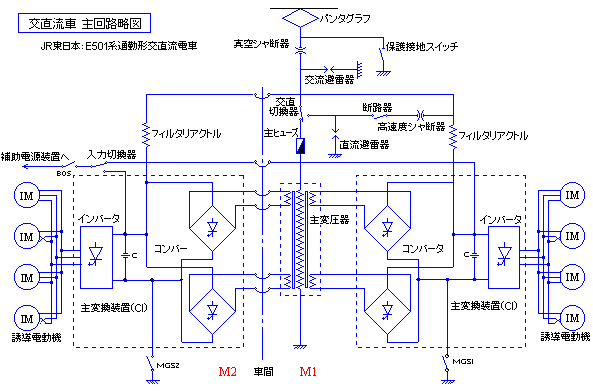5. 電気方式とは? 交流・直流切替点の通過方法は?
1. 電気方式
車両に電気を供給する架線に流れる電気の種類のことで、大きく分けて直流と交流があり、更に電圧と交流の場合は相数、周波数が関係します。
新幹線の電圧は全て単相交流25,000V(実際は負荷等により若干変動している)で、周波数は基本的には電力会社の電源と同じで西日本が60Hz、東日本が50Hzです。しかし、東海道新幹線の東京から静岡までの電力会社の電源周波数は50Hzですが、静岡以西の距離が長いので、JR東海で50Hzを60Hzに周波数変換して架線に電気を供給することにより
東海道・山陽新幹線の周波数は全て60Hzに統一されています。
JR東日本は50Hzが基本ですが、北陸新幹線の場合、軽井沢駅・佐久平駅間に電力会社の50、60Hz境界があり、ここでは車両が自動的に周波数の変化を検知して対応するようになっています。
つまり、「あさま」運用のE2系はどちらの周波数区間でも走行できるようになっています。そればかりでなく、50Hzのある区間を走行中にその変電所が不具合になり突然長野方の60Hz変電所に切り替わり(延長き電)、60Hzの電気がきても問題なく走行できるようになっています。
山形新幹線のような新在直通新幹線の場合は、もともと福島〜山形間や盛岡〜秋田間は単相交流20,000Vで電化されており、そのまま使われています。ということは、車両は25,000Vの既設新幹線区間と20,000Vの新在区間を走行することになりますが、両方の電圧に対応できる変圧器等を採用することにより車両側に特別な変換装置を付けなくても問題なく走行できるようにしています。
JR在来線は、直流が1,500V、交流が単相20,000V、民鉄線は直流が1,500Vが一般的です(あぶくま急行は交流20,000V)。輸送単位の小さいモノレールや新交通では直流750Vや3相交流600Vを剛体電車線から集電する例が多いようです。
旧国鉄線はその電化の歴史等から交流、直流混在でしたが、JR化後はその営業範囲によってJR北海道、九州が交流のみ、JR東海、四国が直流のみ、JR東日本、西日本が交直混在となりました。交直直通運転をするためにはそれ専用の車両が必要です。概ね旧国鉄の車両形式の付け方を踏襲しているJR会社の例だと、その1桁目を見ると電気方式がわかります。
例えば、中央線のE351系特急電車(1〜3が直流専用)、常磐線の
E653系特急電車(4〜6が交直両用)、JR九州の883系交流特急電車(7〜8が交流専用)のとおりです。
交直の接続箇所では地上及び車両側の対策が必要で、地上切換方式としては東北線の黒磯駅が唯一(車上切換も併設)でしたが今は「ひばり」などの特急もないので体験するチャンスは無くなりました。
一方、常磐線の取手駅・藤代駅間にも交直切替箇所があり、ここでは車上切換方式が使われています。常磐線電化の際、茨城県新治郡八郷町にある気象庁の地磁気観測所から35km圏域は直流にすると直流電車のレール漏れ電流が観測所に障害を及ぼすということで取手から北は交流で電化されたもので、特異な例でしょう。
その他の車上切換交直セクションとしては、門司駅構内、北陸本線長浜駅構内、直江津駅・谷浜駅間、湖西線永原駅・近江塩津駅間などにあります。
ヨーロッパでは、交流25,000V 50H(フランスTGV)、15,000V 16.7Hz(ドイツICE)、直流1,500V(フランス在来線等)、3,000V(イタリアETR500)等主な電気方式でも4種類あり、
Thalys(タリス)等の国際列車の一部にはこれら全ての電気方式(当然各国の信号方式にも)に対応した車両もあります。収益性、線路容量等の問題があるようですが、日本では同じ東京駅に平行して入りながら相互運転の計画は無いようです。
2. 交直切換地点の通過方法
走行したまま交直変換する車上切換方式の場合、交直切換はその地点の手前で乗務員が運転席の切換スイッチを扱う、一斉惰行、順次力行方式を採用しています。当然、車両は交直両用の車両でなければならず、たとえば、JR東日本の常磐線に使われているE501系通勤形交直流電車の主回路は下の図のようになっています。なお、この車両の場合、交流区間の補助電源へはトランスの3次巻線と専用の整流器からの供給ではなく主変換装置のコンバータ出力(フィルターコンデンサはDC1700V)から供給する方式となっている。
[交流]→[直流]の流れ(常磐線の取手駅・藤代駅間の例)は
- 交直切換無加圧セクション(約20m程度)の約400m手前にある切換標識によって運転手はマスコンをオフにするとともに、交直切換スイッチを「直」にする。
- マスコンをオフにより、各継電器が動作し、全編成の真空シャ断機(VCB)が解放される。車両は惰行で進む。
-
VCBが解放されると交直切換器が直流側に転換する。
- このように、VCBの「−」側が全て直流側に転換した後、無加圧区間に進入する。
- 続いて直流区間に進入し、パンタグラフに直流電圧を受けた車から順次VCBが投入され加速してゆく。
[直流]→[交流]の流れは
- 切換標識のところでマスコンをオフにし、交直切換スイッチを「交」にする。以下の動作は「交流→直流」の場合と同様。
のようになっています。
運転士がぼんやりしていて交直セクションにそのまま突っ込んだ場合には、交流から直流の場合は主ヒューズの溶断、反対の場合は直流避雷器が短絡して変電所のシャ断器を動作させることにより車両の機器を保護します。
このようなことがないように、最近ではATS-Pのトランスポンダ機能を利用して地上の交直セクション検知用無電源地上子から交直切換地点情報を受信したら直ちに自動的に切り替わるようになっているようです。
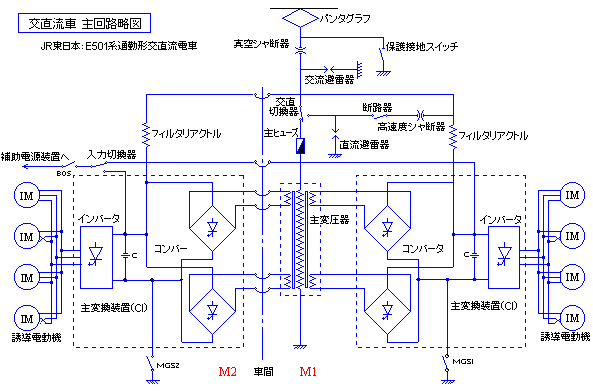
索引に戻る