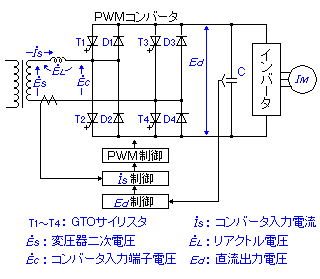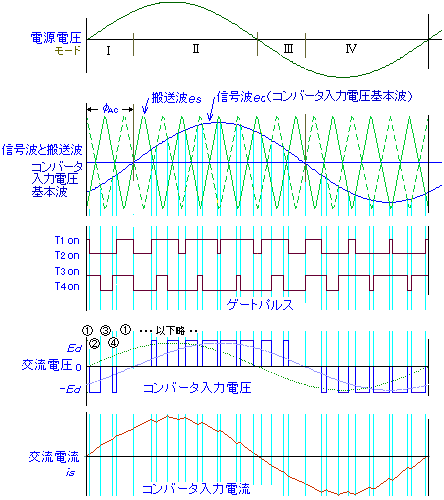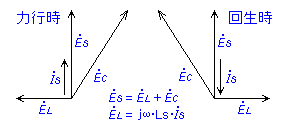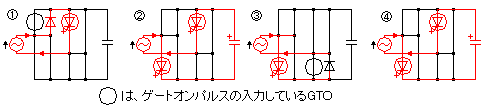| 偁傞帪揰偺揹埑偲廃攇悢 | ON偺帪娫傪抁(挿)偔偟偰丄揹埑傪曄偊傞 | ON-OFF偺娫妘傪抁(挿)偔偟偰丄廃攇悢傪曄偊傞 |
|---|---|---|
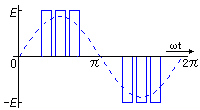 |
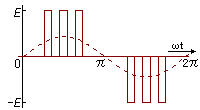 |
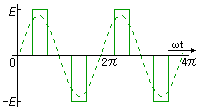 |
| 丂 | 捈棳庡揹摦婡 | 岎棳庡揹摦婡 |
|---|---|---|
| 捈棳揹壔 | 乲揹埑惂屼乴 丂掞峈惂屼 丂捈暲楍惂屼 丂揹婡巕僠儑僢僷惂屼 乲庛傔奅攋惂屼乴 丂奅帴僠儑僢僷惂屼 丂奅帴揧壛椼帴惂屼 |
VVVF僀儞僶乕僞惂屼 乮偡傋傝廃攇悢惂屼偐傜儀僋僩儖惂屼傊乯 |
| 岎棳揹壔 | 僞僢僾惂屼 埵憡惂屼 |
埵憡惂屼亄VVVF僀儞僶乕僞惂屼 PWM僐儞僶乕僞亄VVVF僀儞僶乕僞惂屼 |
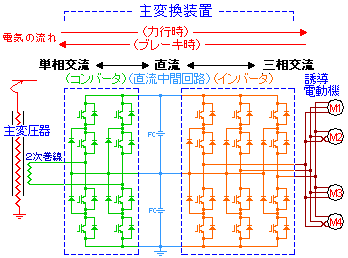 丂 怴姴慄側偳岎棳揹幵偱偼丄僐儞僶乕僞丄僼傿儖僞僐儞僨儞僒丄僀儞僶乕僞丄愙怗婍摍偺庡夞楬婡婍偲柍愙揰惂屼憰抲丄惂屼揹尮側偳偺惂屼夞楬婡婍傗椻媝憰抲傪堦懱敔峔憿偲偟偨惂屼憰抲傪庡曄姺憰抲乮CI乯偲偄偭偰偍傝丄偦偺庡夞楬偼
塃偺恾偺傛偆偵側偭偰偄傑偡丅
丂 怴姴慄側偳岎棳揹幵偱偼丄僐儞僶乕僞丄僼傿儖僞僐儞僨儞僒丄僀儞僶乕僞丄愙怗婍摍偺庡夞楬婡婍偲柍愙揰惂屼憰抲丄惂屼揹尮側偳偺惂屼夞楬婡婍傗椻媝憰抲傪堦懱敔峔憿偲偟偨惂屼憰抲傪庡曄姺憰抲乮CI乯偲偄偭偰偍傝丄偦偺庡夞楬偼
塃偺恾偺傛偆偵側偭偰偄傑偡丅
| 丒 | 曄姺憰抲傪暲楍偵愙懕偟乮懡廳壔乯丄埵憡傪偢傜偟偰弌椡攇宍傪惓尫攇偵傛傝嬤偯偗傞丅偨偲偊偽丄2偮偺僐儞僶乕僞傪暲楍偵愙懕偟偰斃憲攇偺憡嵎塣揮傪峴偆偙偲偱丄p傪憹傗偣偽丄崅挷攇偺師悢偑崅偔側傝丄崅挷攇偺戝偒偝偑彫偝偔側傝傑偡丅 |
| 丒 | LC僼傿儖僞側偳僼傿儖僞傪愝偗傞丅偙偺応崌丄憰抲偑戝偒偔側傞丄摿掕偺廃攇悢偵偟偐岠壥偑側偄応崌偑懡偄側偳偺栤戣偑偁傝傑偡丅 |
| 丒 | PWM惂屼傪梡偄傞偙偲偵傛偭偰崅懍偵惂屼傪峴偄惓尫攇偵嬤偯偗傞丅GTO傛傝傕崅懍僗僀僢僠儞僌偑壜擻側IGBT傪梡偄傞偙偲偵傛偭偰峏偵偱崅挷攇懳嶔偑
恑傫偱偄傑偡丅僷儖僗暆傕堦掕暆偱側偔丄攇宍偺廃曈偱嫹偔拞墰晹偱峀偄僷儖僗偲偟偰掅師崅挷攇傪側偔偟偨嬤帡惓尫攇PWM宍偑嵦梡偝傟偰偄傑偡丅
峏偵丄埵憡傪惂屼偟偰柍岠揹椡偺曗彏乮椡棪傪1偵偡傞乯傕壜擻偵側傝傑偡丅 |
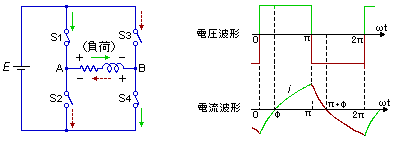
| 偁傞帪揰偺揹埑偲廃攇悢 | ON偺帪娫傪抁(挿)偔偟偰丄揹埑傪曄偊傞 | ON-OFF偺娫妘傪抁(挿)偔偟偰丄廃攇悢傪曄偊傞 |
|---|---|---|
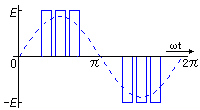 |
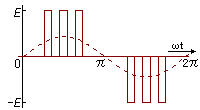 |
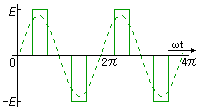 |
|
丂 幚嵺偺僀儞僶乕僞偼塃恾乮扨憡僽儕僢僕宍僀儞僶乕僞偺椺乯偺傛偆偵側偭偰偍傝丄僗僀僢僠儞僌慺巕偲偦傟偵媡暲楍偵愙懕偝傟偨僟僀僆乕僪偱峔惉偝傟偰偄傑偡丅
丂 尨棟恾偵偁傞僗僀僢僠偺嶌梡傪偡傞偺偑僷儚乕僨僶僀僗偱丄GTO傗IGBT偑巊傢傟傑偡丅 丂 僟僀僆乕僪偼丄揹埑偲斀懳曽岦偵棳傟傞揹棳傪棳偡偨傔偺傕偺偱丄娨棳僟僀僆乕僪偲偄傢傟偰偄傑偡丅 |
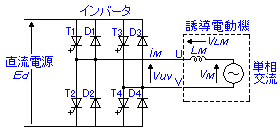 |
|
丂 偙偺惂屼偵偼PWM惂屼偑梡偄傜傟傑偡偑丄扨憡偺PWM弌椡揹埑攇宍e偼塃恾偺傛偆偵斃憲攇乮carrier wave乯偲屇偽傟傞嶰妏攇es偲婎杮攇偵巊梡偡傞
怣崋攇乮signal wave乯偲屇偽傟傞惓尫攇eo傪斾妑偟偰僗僀僢僠儞僌慺巕傪ON丄OFF 偡傞偙偲偵傛傝摼傜傟傑偡丅 偮傑傝丄
eo亜es偺偲偒丄T1T4偑ON乮T2T3偼OFF乯偱丄e亖Ed
丂 偙偺傛偆偵偡傞偲丄惓尫攇忬偵僷儖僗暆傪曄壔偝偣傞偙偲偑偱偒傞偨傔丄惓尫攇PWM偲屇偽傟丄弌椡偵惓尫攇傪朷傓僀儞僶乕僞偺惂屼偵巊梡偝傟傑偡丅
eo亙es偺偲偒丄T2T3偑ON乮T1T4偼OFF乯偱丄e亖-Ed 丂 僀儞僶乕僞弌椡揹埑攇宍偼丄PWM攇宍偱偡偑丄偦偺婎杮攇偲揹摦婡撪晹揹埑倁M偺娫偵偼冇M偺埵憡嵎偑偁傝丄偙偺椉幰偺嵎暘偑LM偵偐偐傞揹埑偱丄 寢壥揑偵iM偱帵偝傟傞弌椡揹棳傪棳偟傑偡丅偙偺倁M偲岎棳揹棳iM偑幚嵺偵僩儖僋傪敪惗偟傑偡丅 丂 偙偺恾偐傜傢偐傞傛偆偵斃憲攇乮僉儍儕儎乯廃攇悢偼PWM攇宍偺僗僀僢僠儞僌廃攇悢偲堦抳偟傑偡丅 丂 廬偭偰丄僉儍儕儎廃攇悢傪忋偘傞偩偗偱嵟掅師偺崅挷攇偺廃攇悢傪忋偘傞偙偲偑偱偒丄弌椡僼傿儖僞偺彫宍壔偑壜擻偵側傝傑偡丅 |
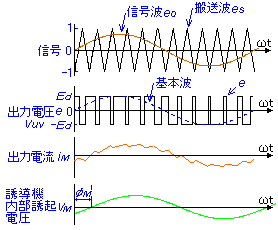 |
|
丂 偙偙偱丄惓尫攇eo偺怳暆傪曄偊傞偲PWM攇宍偺婎杮攇偺怳暆傪曄偊傞偙偲偑偱偒傑偡丅椺偊偽丄eo亖0偲偡傟偽丄e偼僉儍儕儎廃攇悢偲摍偟偄曽宍攇偲側傝婎杮攇惉暘偼娷傑傟偢丄eo亖1側傜丄e亖Ed偲側傝傑偡丅
丂 偙偺抣傪曄挷棪偲偄偄丄捈棳揹埑偺抣丄偮傑傝丄愗傝崗傑傟偨岎棳揹埑偺攇崅抣偵懳偟偰偳傟偩偗偺岎棳婎杮揹埑偑摼傜傟傞偐偲偄偆妱崌傪帵偟傑偡丅 |
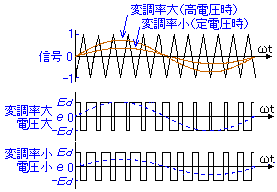 |
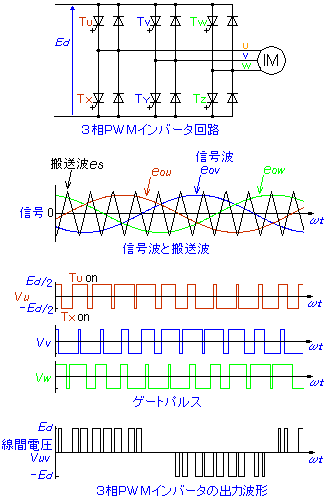 丂 捈棳揹尮俤倓偺揹埑偼丄嵼棃慄偺応崌丄捈棳嬫娫偺偒揹揹埑偑1500倁側偺偱丄1500倁偲偟丄岎棳嬫娫偱偼僐儞僶乕僞偱岎棳20000倁傪捈棳1500倁偺拞娫捈棳揹尮偵曄姺偟偰偄傑偡丅
丂 捈棳揹尮俤倓偺揹埑偼丄嵼棃慄偺応崌丄捈棳嬫娫偺偒揹揹埑偑1500倁側偺偱丄1500倁偲偟丄岎棳嬫娫偱偼僐儞僶乕僞偱岎棳20000倁傪捈棳1500倁偺拞娫捈棳揹尮偵曄姺偟偰偄傑偡丅