6. 鉄道車両のブレーキ方式とは?
1.鉄道車両用ブレーキの要件
走ることと同様に安全に停まることが重要です。鉄道車両のブレーキに関しては次のような点を満足させる必要があります。
(1) 法律上の規制
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第69条(ブレーキ装置)に次のように規定されており、これがブレーキ装置の基本です。
第69条 車両には、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。
一 車両を確実に減速し、又は停止させることができること。
二 組成した車両に乗務員室からの操作により連動して作用すること。
三 振動、衝撃等によりその作用に支障を及ぼすおそれのないこと。
四 制動力を連続して作用させることができること。
五 組成した車両が分離したときに自動的に作用すること。
六 車両を急速に停止させることができること。ただし、特殊車にあっては、この限りでない。
七 制動力の供給源を確保することができないことにより、その作用に支障を及ぼすおそれのある場合は、発車することができないこと。ただし、蒸気機関車であって警報装置等を設置した場合は、この限りでない。
2 車両には、前項のブレーキ装置のほか、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。
一 留置中の車両の転動を防止することができるものであって前項第三号の基準に適合する装置。ただし、当該装置を有する他の車両に固定連結すること等により、留置中に車両の転動を防止する場合は、この限りでない。
二 前項のブレーキ装置が故障した場合に使用することができる独立したブレーキ機能を有するものであって前項第一号、第三号及び第四号の基準に適合する装置。ただし、機関車、旅客車(客車に限る。)、貨物車(貨車及び荷物車に限る。)及び特殊車は除く。
更に、解釈基準には
・ 留置中の車両の転動を防止することができる装置(留置ブレーキ装置)を設ける。
・ 電車・内燃動車に、常用のブレーキ装置が故障した場合に使用できる独立したブレーキ装置(保安ブレーキ装置)を設ける。
・ 新幹線には、独立して作用する2系統以上のブレーキ指令系を有する。
等詳細な規定があります。
(2) ブレーキ性能
在来線の場合、旧「鉄道運転規則」により、非常制動による列車の制動距離は600m以下とすることが規制されていましたが、新省令では第106条(列車防護)の解釈基準に、次のように表現されています。
5 新幹線以外の鉄道における非常制動による列車制動距離は、600m以下を標準とすること。ただし、防護無線等迅速な列車防護の方法による場合は、その方法に応じた非常制動距離とすることができる。
従来はこの非常制動距離600mを基本にしていましたが、その距離は車両の性能や列車防護の方法等との関係で決まるものという考え方になっています。
踏切がなく線形もよいほくほく線では、160km/h 運転が実現しています。特認で、下り10‰勾配で1200m以内に停まるという条件が付けられており、従来の進行(緑:G)の上位の信号GG信号を設けて可能になりました。なお、この高速走行を行うにあたっては設備の性能のみでなく乗務員の疲労、信号の視認性が十分に検討されています。
新幹線の場合は、制動距離では規制せず、新幹線構造規則により下表の数値以上になるように減速度で規制しています。
新幹線の規制減速度(非常ブレーキの場合)
| 速度(km/h) | 70以下の場合 | 70をこえ110以下 | 110をこえ160以下 | 160をこえ230以下 | 230をこえる場合 |
| 減速度(km/h/s) | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.5 |
*平坦線で直線上 *旅客車は空車の状態
これらの条件を満足しながら良好な乗り心地の維持、ブレーキ材料等摩耗品の摩耗量削減等を図らなければなりません。
更に、雨の降り始めなどは大変滑りやすいので強いブレーキはかけにくいのですが、一方では600m以内に止めなければならないなど、相反する条件を満足する必要があります。
この摩擦の問題は加速時も同じことが言え、重要な課題になっています。
電車に乗っていると車輪がコトコト(ガタガタ)音を立てて走っていることがありますが、車輪−レール間の摩擦係数が雨などで下がって車輪が回転しないで滑走して傷ができたためのもので、それをフラットができた
といっています。騒音、乗り心地に悪影響を与えるばかりでなく、軸受などの安全上の問題にもなるため、空転・滑走をおこさないような制御や在姿車輪旋盤による車輪踏面削正が行われています。
(3) 機械ブレーキのメカニズム
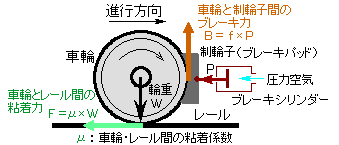
基本となる空気ブレーキ(踏面)の場合、車輪と制輪子間のブレーキ力Bと車輪とレール間の粘着力Fとの関係は右図のようになっており、
ブレーキ力Bが粘着力Fより大きい場合は車輪はロックされ滑走するのでB≦Fの関係を保たなければなりません。
ブレーキ力はブレーキシリンダーの圧力を制御して行いますが、BもFも接触面や速度等の条件によって変化する摩擦力をベースにしているため
それらの特性を十分考慮しなければなりません。
2.ブレーキ性能と方式
ブレーキの仕様を見る際には、ブレーキ性能とブレーキ方式が関係します。ブレーキ性能は一般に、「減速度」という項目で表現します。たとえば減速度3.0km/h/sは1秒間に3.0km/hだけ速度が下がるということで、単純に計算すると、120km/hからブレーキをかけると
40秒で停車し、その間約670m走るということです。安全に「600m以内」に停まるためには非常時の減速度を更に上げる必要がありますが
粘着力の制約もあり現状では最高速度130km/h程度が限度と言われています。更に速度向上するためには踏切を無くして特認をもらうか、
レールブレーキを併用することなどが必要になるようです。
常用最大減速度は車両の最高速度、用途等により、2〜5km/h/sですが、あまり大きくするとブレーキ時に乗り心地を損ねる問題や
車輪の回転が止まったままレールの上を滑って(滑走)車輪に傷(フラットなど)ができて走行中「かたかた」と音がしたり安全上の問題が生じる場合があります。
通常、最大減速度を数等分したブレーキシリンダ圧力がブレーキハンドルの位置で選択でき、そのブレーキ力(減速度)は速度に関わらず一定となりますが、
実際には前述のとおり摩擦係数が変化するとブレーキ力もそれに応じて変化してしまいます。
ブレーキ方式は車両諸元表を見ると、最近の電車では「回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ」のように記載されており、この場合、
「ブレーキ力の指令には空気圧でなく電気を使用する空気ブレーキを使い、運動エネルギーを電気エネルギーに変換して架線側に返す(電力回生)ブレーキも併用する」ということです。
「回生ブレーキ併用」と言っていますが、どちらかというと回生ブレーキを第1優先とし、低速時等やむを得ない場合のみ空気ブレーキを使用して制輪子等の摩耗を極力小さくする使い方が通常です。
かつては、各車に「元空気だめ管」「ブレーキ管」「直通管」の3本の管を貫通させてブレーキ操作を行う「発電ブレーキ併用電磁直通空気ブレーキ」がよく使用されてましたが、
現在ではこの方式が標準になってきており、列車に引き通す空気管は電動圧縮機とつながった空気元としての「元空気だめ管」1本だけになっています。
車両間の渡りは連結器内に組み込まれているので外からは見えません。
鉄道車両の場合、自動車のようなペダルではなく運転台にあるハンドルを操作することによりブレーキが作用しますが、ハンドルは大きく分けて1ハンドルマスコンといわれる加速・ブレーキ共用のハンドルとブレーキ専用ハンドルの2つのタイプがあります。このハンドルを操作することにより所定の大きさのブレーキがかかりますが、異常時等にはブレーキ操作と関係なく自動的に作用するようにもなっています。
3.ブレーキの分類
鉄道車両用のブレーキには色々な方式、種類がありますが次のような分類で整理してみました。
(1) ブレーキの方式別分類
ア、空気ブレーキ
5kg/cm2(490kPa)程度の圧縮空気をブレーキシリンダーに送ってブレーキ作用を行う方式の総称で、方式で分類すると次のようになる。なお、新幹線は空気力を増圧シリンダーで油圧に変換してブレーキシリンダーに送る。
○自動空気ブレーキ
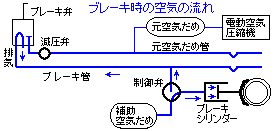 列車に貫通している5kg/cm2常時加圧の「ブレーキ管」圧力を運転台のブレーキ弁で空気を逃がして減圧することにより各車に装備した制御弁を動作させ、この弁を介して予め圧力空気を蓄えておいた「補助空気だめ」の空気をブレーキシリンダーに送り、ブレーキ管の減圧量に見合ったブレーキシリンダー圧力を発生させてブレーキがかかる。ブレーキ弁には「緩め位置」、「ブレーキ位置」、「重なり位置」、「非常位置」がある。 列車に貫通している5kg/cm2常時加圧の「ブレーキ管」圧力を運転台のブレーキ弁で空気を逃がして減圧することにより各車に装備した制御弁を動作させ、この弁を介して予め圧力空気を蓄えておいた「補助空気だめ」の空気をブレーキシリンダーに送り、ブレーキ管の減圧量に見合ったブレーキシリンダー圧力を発生させてブレーキがかかる。ブレーキ弁には「緩め位置」、「ブレーキ位置」、「重なり位置」、「非常位置」がある。
列車が分離したときになどにも作用するフェールセーフのブレーキであり、ブレーキ管圧力の増減でブレーキ力を調節できるので広く採用されていた。長大編成では先頭車から順にブレーキがかかるため後方車両では応答遅れがある。
各車に電磁弁を設置して電気指令により一斉に制御するようにして列車全体としてのブレーキ応答速度を早めた方式に電磁自動空気ブレーキがある。
|
○直通ブレーキ
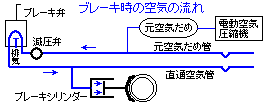 列車に貫通している常時は無圧の「直通管」を運転台のブレーキ弁を扱って増圧制御を行い、直通管から直接か中継的に働く空気弁を介在させて直通管と同等の空気圧をブレーキシリンダーに送りブレーキをかける。 列車に貫通している常時は無圧の「直通管」を運転台のブレーキ弁を扱って増圧制御を行い、直通管から直接か中継的に働く空気弁を介在させて直通管と同等の空気圧をブレーキシリンダーに送りブレーキをかける。
一般に小刻みなブレーキのかけ、緩めを繰り返し行うことができるので操作性は優れているが、2両以上の編成では列車分離の際にブレーキが利かなくなる大きな欠点があり、上記の自動ブレーキと組み合わせたり、常時加圧の非常管を引き通し、各車に非常弁を設け、列車分離に対応する方法がある。
各車に電磁弁を設置して電気指令により一斉に直通管圧力を制御するようにしてこの圧力で編成各車の中継弁を作用させてブレーキ作用と緩め作用の応答を早めた方式に電磁直通空気ブレーキがあるが、列車分離の際の問題はやはり残っているので何らかのバックアップが必要である。
|
○電気指令式空気ブレーキ
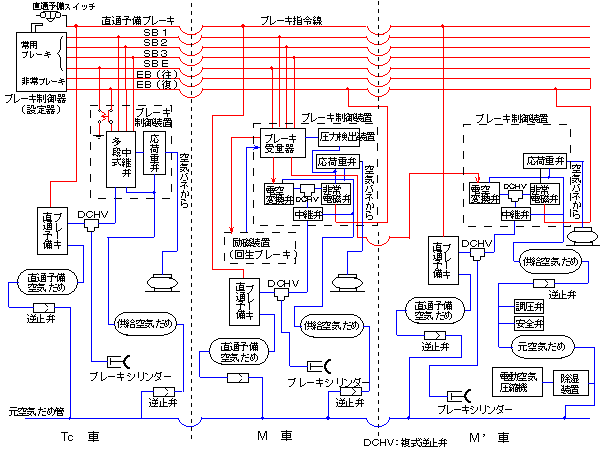 現在、電車、気動車等に標準となっている方式で、
右図のように運転台からのブレーキ指令を全て電気的に行い、各車かユニット単位で電気指令を空気指令に変換し、その空気指令により中継弁を働かせ、その作用によってブレーキシリンダー圧力を得る方式で、電車の場合はブレーキ指令が電動車の電気ブレーキ制御装置にも送られ、電空協調制御がなされる。 現在、電車、気動車等に標準となっている方式で、
右図のように運転台からのブレーキ指令を全て電気的に行い、各車かユニット単位で電気指令を空気指令に変換し、その空気指令により中継弁を働かせ、その作用によってブレーキシリンダー圧力を得る方式で、電車の場合はブレーキ指令が電動車の電気ブレーキ制御装置にも送られ、電空協調制御がなされる。
指令は全て電気的に送られるので引き通し管は電動空気圧縮機とつながって空気元となる「元空気だめ管」のみでよい。
列車分離に対しても、常時加圧の往復引き通しを使用してこの線が無圧(=断線)になったら非常ブレーキがかかるようになっている。
|
| 図中の主な機器の役割 |
| ブレーキ制御器(設定器) | ハンドルなど運転台にあるブレーキ指令を行うための機器 |
| ブレーキ受量器 | ブレーキ指令と応荷重信号などを受け、作用させるべき最適ブレーキ量を演算し、電気ブレーキと空気ブレーキ指令を発生する。 |
| ブレーキ制御装置 | 床下に装備される空気ブレーキ用の弁類・機器をまとめてユニット化したもので、ブレーキ指令により弁類、機器を動作させてその車両のブレーキシリンダー圧力を制御する。ブレーキ受量器内蔵のものもある。 |
| 電空変換弁 | 電気信号を空気圧に変換する弁で、電気信号の大きさに応じた空気圧として出力する。
|
| 中継弁 | 指令空気圧力を受けて中継的に空気流量増幅を行う弁で、供給空気だめの空気を呼び出して指令圧力とほぼ同等な圧力空気をブレーキシリンダーに送る。 |
| 応荷重弁 | 空気バネ内圧等で乗客の荷重を検知しその大きさに応じて空気ブレーキ力を制御するための弁
|
| 電磁弁 | 電磁コイルを励磁、消磁することによって内部の空気通路を切り替える弁 |
| 元空気だめ | 電動空気圧縮機で圧縮された圧力空気をアフタークーラと除湿装置を通して冷却し、清浄な乾燥された圧力空気をブレーキ装置、主制御器、戸閉め装置などに供給するために貯える。 |
| 供給空気だめ | 元空気だめから供給された圧縮空気を、通常使用する空気ブレーキに供給するために貯える。 |
| 複式逆止弁 | いずれか一方の通路をブレーキシリンダーに連絡し、他方を遮断する。 |
| 電動空気圧縮機 | 床下で時々「たたたた・・」と運転音がするのがこれで、様々な用途に使われる圧力空気を作る重要な機器である。 |
イ、電気ブレーキ
電動機を制御してブレーキ時には発電機として使い、運動エネルギーを電気エネルギーに変換してからブレーキに利用するものを電気ブレーキと言っている。空気ブレーキの制輪子のような摩耗材料が不要なので電気ブレーキでブレーキが利く速度範囲は極力電気ブレーキでカバーするように制御し、一般に低速になって起電力が小さくなり架線に電気を返せなくなると自動的に空気ブレーキに切り替わるように制御している。すなわち、電気ブレーキ力+空気ブレーキ力=必要ブレーキ力という演算を常に行っている。発電ができないような事態になった場合(「電制フェール」と言っている)にも当然所要の空気ブレーキが働くようになっている。
○発電ブレーキ
電気ブレーキは電動機を発電機として使用するブレーキなので、全て発電ブレーキと言っていたが、かつては電気エネルギーを自車に搭載した抵抗器で消費する方法が主流だったのでこのことを次項の回生ブレーキと対比させて発電ブレーキと言うことが多い。
300系新幹線等東海道・山陽新幹線電車で付随車がある車両には、ECB(Eddy Current Brake)といって、電動車で発電した電気を付随車の車軸に付けたディスクに相対するコイルに流し、ディスクに渦電流を発生させて相互作用によりブレーキ力を得る非接触式のディスクブレーキが使われている。
|
○(電力)回生ブレーキ
現在の電車では発電した電気をパンタグラフから架線に戻してやり他の加速中の車両等に消費させる省エネルギー性に優れた(電力)回生ブレーキが主流となっている。
回生ブレーキの場合、直流き電ではき電変電所で一方通行なので、消費してくれる車両がないとブレーキ力が不足するためその分を空気ブレーキが補うことになるが、空気ブレーキ動作による摩耗部品の取替経費が増えるので変電所に抵抗器を設置してここでエネルギーを消費させるやり方や補助的な抵抗器を積むを場合がある。交流き電では変電所を経由して他の一般負荷とつながっており、それらがエネルギーを消費してくれる。
VVVFインバータ制御にベクトル制御を採用するなどして全ての速度域で回生ブレーキを使うための技術開発が進められている一方、回生エネルギーを有効に消費してくれる負荷がない等の場合のために少量の抵抗器を積んで発電・回生併用とした車両もある。
|
ウ、空力ブレーキ
超高速鉄道として開発が進められているリニア車両に採用されたもので、ブレーキ時に車体上部の空力ブレーキ板を車体直角に立てて断面積を大きくし空気抵抗を利用する。空気抵抗は速度の2乗に比例すると言われ、高速域では大きな効果を発揮するが低速になると効果が無くなるので別途電気あるいは機械的なブレーキが必要になる。
JR東日本の次世代新幹線試作車「FASTECH360」にもこの方式が採用されている。
(2) ブレーキ力を発生させる場所による分類
| 踏面ブレーキ | 主にブレーキシリンダー(BC)に圧力空気を供給してピストンの押棒を動かし制輪子を車輪踏面に押しつける方式。 |
| ディスクブレーキ | 付随車や新幹線で採用されている方式で、車輪側面又は車軸に取り付けられたブレーキディスク側面にブレーキシュー(ライニング)を押しつける方式。電気ブレーキに分類される渦電流ブレーキ(ECB)でもディスクが使われている。 |
| レールブレーキ | 台車にブレーキ材を付けておき、レールに押しつける方法と渦電流を発生させる方法とがある。峠のシェルパと言われた信越本線の碓氷峠専用電気機関車EF63では急勾配用として電磁吸着レールブレーキを持っていた。 |
(3) ブレーキの用途別分類
| 常用ブレーキ | 通常使用するブレーキで、最大ブレーキ力を7段階に分割してハンドルの位置により1〜7ノッチ(又はステップ)としたタイプが多い。1Nが最も弱く、7Nが最も強くて通常常用最大ブレーキと言われる。
かつて、在来線車両では非常ブレーキ力は常用最大ブレーキ力と同等な例もあったが、最高速度130km/h運転を開始したJR西日本の223系2000番台は、常用最大減速度4.3km/h/s、非常減速度5.2km/h/sとなっている。
非常時の減速度が大きいのは、最高速度向上によって同じブレーキ力ではブレーキ距離が延びるが、踏切が無い等の特殊な場合を除いて鉄道運転規則(運輸省令)によって「非常ブレーキ距離を600m以下にする」という大原則があるためであり、
最高速度の向上はこれを満足できるか否かにかかっていると言っても過言ではなく、通常のブレーキのみでは130km/hが限度といわれるが、更に技術開発が進められている。
ATO(自動列車運転装置)を使った車両では、コンピュータで細かな制御ができるようにATO運転ではブレーキ段数を倍にして制御を行う例が多い。 |
| 非常ブレーキ | 前方線路上に異常がある等の非常時にブレーキハンドルを「非常」位置にした場合や列車分離などの重大事故時には自動的に確実にブレーキが作用するように、非常用ブレーキを持っている。
電気指令の場合、常時加圧の往復引き通し線を使用し、無加圧(たとえば列車分離)になると非常ブレーキ力が作用するようになっている。ブレーキ力の大きさとしては、在来線では常用最大とほぼ同じか高速車両では約2割増、新幹線では4か5割増である。 |
| 緊急ブレーキ | 新幹線の場合で、列車分離、空気管圧力降下等時に動作し、応荷重機能は備えていない。 |
| 補助ブレーキ | 新幹線の場合で、ブレーキ制御装置不良、ブレーキ指令線断線、救援時等に用いる。ブレーキ力は速度に関係なく一定で、運転台の設定スイッチ及び各車の配電盤スイッチを扱う。 |
| 直通予備ブレーキ | 保安ブレーキともいい、昭和46年3月に富士急行線で列車が踏切でトラックと衝突した後、空気管が破損してブレーキが利かなくなり、
下り勾配を暴走して脱線、転覆し多くの死傷者が出たことに鑑み、運輸省の指導で整備することになったもので元空気だめ圧力が不足した時と直通予備ブレーキスイッチを扱うと作用する。常用ブレーキ装置が故障したときに
自動的に作用するようにしたブレーキ |
| 耐雪ブレーキ | 降雪時、ブレーキディスクと制輪子間に雪のかみ込みを防止するため制輪子を軽く押しつけ、加熱する目的で装備している。速度は110km/h以下、耐雪ブレーキスイッチ扱い、ブレーキハンドル扱い条件で動作する。 |
| 抑速ブレーキ | 下り勾配で抑速指令が入力されるとその時の速度を設定速度として抑速制御(回生)を行う。 |
| ATCブレーキ | 運転保安方式にATC方式を採用した線区を走る車両では指定速度を超過しそうになったら乗務員が操作しなくても自動的にATCブレーキがかかる。 |
4.ブレーキの効果、省エネルギー性等を高めるための技術
より安全で効果的に、より乗り心地に悪影響を与えないように、摩擦材料の摩耗量を減らすように等様々な工夫がされています。電力回生以外でも次のような工夫がされています。
| 遅れ込め制御 | 通常回生ブレーキが使われるが、ブレーキ力が粘着限界を超えない範囲で高くとり、付随車の必要なブレーキ力を電動車の電気ブレーキ力で負担し、負担しきれない分はもともとの付随車に空気ブレーキ力を作用させる。遅れ込め制御で
編成としての電力回生率が向上し、付随車の制輪子の摩耗を低減できる。 |
| 滑走検知・再粘着制御 | ブレーキをかけた場合に車輪がレールに対して相対すべりを起こし始めたときそれを素早く検知してすべり状態がある値に達したときに滑走と判断し、ブレーキ力を緩めて再粘着を促し、再粘着したことを確認することによりブレーキ力を復帰させる制御。
主電動機に取り付けられた速度発電機(T車系は軸端の速度発電機)からパルスを得て各軸の回転速度を計算し滑走状態を検知する。
車輪の滑走を検知する方法としては、速度差検知、すべり率検知、減速度検知(微分検知)の3つがあり、
単独よりは2つ以上の機能を併用して高性能化を図ることが多い。ある一定時間以上滑走が継続したような場合は異常と見なし、通常の状態に復帰させる。 |
| 応荷重制御 | 空気ばね圧力を検知して乗客の多少によってブレーキ力を増減し、一定の減速度が得られるように自動的に制御する。 |
| 電空協調制御 | 全て電気ブレーキで停車できればそれにこしたことはないが、低速になって電気ブレーキ力が低下する際や電気ブレーキが故障する際には空気ブレーキが確実に動作する必要がある。
空気ブレーキ力=所要ブレーキ力−電気ブレーキ力となるような電空演算制御を行って電気ブレーキと空気ブレーキが協調して必要なブレーキ力を確保するようにしている。
|
| 速度−粘着パターン(μパターン)制御 | 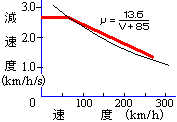 車輪・レール間の粘着係数μは高速では低下することが試験から判明したので新幹線では湿潤時のμを 13.6/(V+85) のように変化するとしており、これに応じで同じブレーキノッチでも減速度が速度に応じて変化するように制御している。
車輪・レール間の粘着係数μは高速では低下することが試験から判明したので新幹線では湿潤時のμを 13.6/(V+85) のように変化するとしており、これに応じで同じブレーキノッチでも減速度が速度に応じて変化するように制御している。
右図の赤線はE2系新幹線の最大ノッチでの設定減速度である(70km/h以下で2.69km/h/s一定、275km.hで1.44km/h/s程度)。最近の新幹線車両ではやや大きめの減速度値になっているようだ。
在来線では一般にブレーキノッチに応じて一定減速度だが、最高速度が高い車両ではμを考慮して減速度を変化させる例が出てきている。 |
| 定速制御 | 定速指令が入力されるとその時の速度を設定速度として定速制御(力行・
ブレーキ)を行う |
索引に戻る
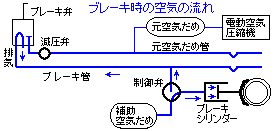 列車に貫通している5kg/cm2常時加圧の「ブレーキ管」圧力を運転台のブレーキ弁で空気を逃がして減圧することにより各車に装備した制御弁を動作させ、この弁を介して予め圧力空気を蓄えておいた「補助空気だめ」の空気をブレーキシリンダーに送り、ブレーキ管の減圧量に見合ったブレーキシリンダー圧力を発生させてブレーキがかかる。ブレーキ弁には「緩め位置」、「ブレーキ位置」、「重なり位置」、「非常位置」がある。
列車に貫通している5kg/cm2常時加圧の「ブレーキ管」圧力を運転台のブレーキ弁で空気を逃がして減圧することにより各車に装備した制御弁を動作させ、この弁を介して予め圧力空気を蓄えておいた「補助空気だめ」の空気をブレーキシリンダーに送り、ブレーキ管の減圧量に見合ったブレーキシリンダー圧力を発生させてブレーキがかかる。ブレーキ弁には「緩め位置」、「ブレーキ位置」、「重なり位置」、「非常位置」がある。
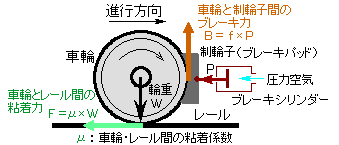
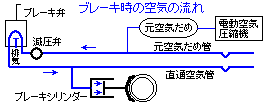 列車に貫通している常時は無圧の「直通管」を運転台のブレーキ弁を扱って増圧制御を行い、直通管から直接か中継的に働く空気弁を介在させて直通管と同等の空気圧をブレーキシリンダーに送りブレーキをかける。
列車に貫通している常時は無圧の「直通管」を運転台のブレーキ弁を扱って増圧制御を行い、直通管から直接か中継的に働く空気弁を介在させて直通管と同等の空気圧をブレーキシリンダーに送りブレーキをかける。
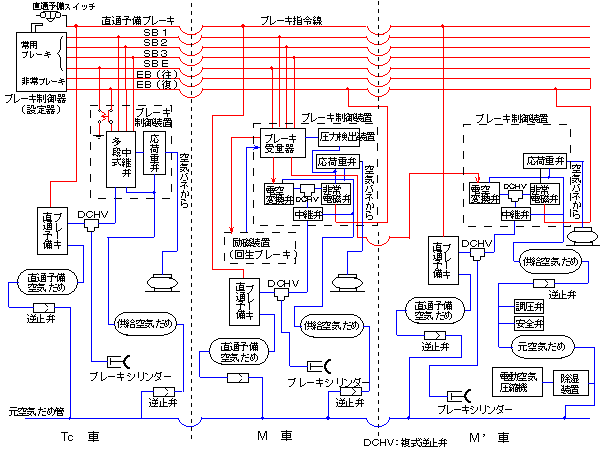 現在、電車、気動車等に標準となっている方式で、
右図のように運転台からのブレーキ指令を全て電気的に行い、各車かユニット単位で電気指令を空気指令に変換し、その空気指令により中継弁を働かせ、その作用によってブレーキシリンダー圧力を得る方式で、電車の場合はブレーキ指令が電動車の電気ブレーキ制御装置にも送られ、電空協調制御がなされる。
現在、電車、気動車等に標準となっている方式で、
右図のように運転台からのブレーキ指令を全て電気的に行い、各車かユニット単位で電気指令を空気指令に変換し、その空気指令により中継弁を働かせ、その作用によってブレーキシリンダー圧力を得る方式で、電車の場合はブレーキ指令が電動車の電気ブレーキ制御装置にも送られ、電空協調制御がなされる。
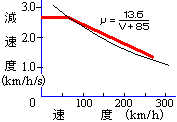 車輪・レール間の粘着係数μは高速では低下することが試験から判明したので新幹線では湿潤時のμを 13.6/(V+85) のように変化するとしており、これに応じで同じブレーキノッチでも減速度が速度に応じて変化するように制御している。
車輪・レール間の粘着係数μは高速では低下することが試験から判明したので新幹線では湿潤時のμを 13.6/(V+85) のように変化するとしており、これに応じで同じブレーキノッチでも減速度が速度に応じて変化するように制御している。